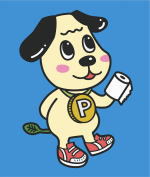2016年06月03日
卵巣年齢が高い方(低AMH)
卵巣年齢と言う言葉が使われ始めたころから、AMH(抗ミュラー管ホルモン)と呼ばれるホルモンの測定が、不妊クリニックで一気に広がりました。最近では、検査で測定してもらう方が多くなったように思います。
AMHは、原始卵胞→→→成熟卵胞に成長していく時に、卵子から分泌されるホルモンです。

AMHが高いと、それだけ成長途中の卵子が卵巣内にストックされるため、妊活や不妊治療には有利だと言われています。
AMHの数値は、20代と比べ、30代後半では約半分、40代ではさらにその半分にまで減ってしまうとされますが、20代でも40代の数値の方や、40代でも30半ばくらいの数値を維持している方もいます。
一般にAMHは、卵巣内に残る卵のもとが、どれくらい残っているかを推定する数値と言われていますが、卵の質を反映するものではないため、低AMHであっても、必ずしも不妊とは限りません。
ただし、AMHが低い方は、クリニック等での治療において、ホルモン剤による卵巣への刺激が強くなる傾向があります。
残っている卵が少ないので、卵巣を強く刺激して、排卵に導こうとするのは合理的かもしれません。
そのような状況で、漢方薬はどのように介入できるのでしょうか?
卵のストックが少ない状況とは、一般に更年期に近づけば誰しも起こる状況なので、卵巣年齢が高いとされる低AMHの方には、更年期に起こりやすい血流不良があると考え、血流を改善し、規則正しい排卵を促す漢方婦人薬を使うことになります。
また、卵に質についてですが、抗酸化作用のある漢方薬が対応します。
卵は、主に酸化ストレスによって老化するといわれています。
酸化ストレスとは、呼吸により取り込んだ酸素の一部が悪さをして、身体を錆びさせていく事ですが、病気や老化の原因になることとが知られています。
卵の酸化ストレスは、生きてきた時間に比例するので、卵巣年齢が高くても、卵の質まではそれほど悪くない場合があります。
AMHが低くても、妊娠する方がいるのは、卵の量的な低下ほどに質的低下を免れていたの可能性があります。
卵のグレードと言う表現があり、各施設では様々な基準を設けて卵の質を評価していますが、遺伝情報である卵の染色体の質を判定しているわけではありません。卵の見た目が良く、見た目が良い方が妊娠率に良い結果を及ぼすという視点で、グレードを判定しているようです。
一方で、子宮の状態を整えることも大切です。
胚盤胞まで育ったので、子宮へ移植した時に、着床しないケースがあります。
この場合は、子宮内膜の状態をよくする漢方薬が応じます。
子宮は、子を育てるベッドのようなものです。胎児と母親は臍帯(へその緒)で結ばれますが、それは妊娠成立後、3か月程度経過してからです。受精卵と子宮は、着床後に先ずは血流で結ばれる必要があります。
血流改善を得意とする漢方薬では、子宮の状態をよくするために、卵巣年齢が高い方でも早い段階から使用します。
AMHが低く卵巣年齢が高いとされる方には
①血流を整え
②酸化ストレスを低減し
③子宮内膜の状態を改善する
というスタンスで、不妊症漢方療法をお使いいただいています。
AMHは、原始卵胞→→→成熟卵胞に成長していく時に、卵子から分泌されるホルモンです。

AMHが高いと、それだけ成長途中の卵子が卵巣内にストックされるため、妊活や不妊治療には有利だと言われています。
AMHの数値は、20代と比べ、30代後半では約半分、40代ではさらにその半分にまで減ってしまうとされますが、20代でも40代の数値の方や、40代でも30半ばくらいの数値を維持している方もいます。
一般にAMHは、卵巣内に残る卵のもとが、どれくらい残っているかを推定する数値と言われていますが、卵の質を反映するものではないため、低AMHであっても、必ずしも不妊とは限りません。
ただし、AMHが低い方は、クリニック等での治療において、ホルモン剤による卵巣への刺激が強くなる傾向があります。
残っている卵が少ないので、卵巣を強く刺激して、排卵に導こうとするのは合理的かもしれません。
そのような状況で、漢方薬はどのように介入できるのでしょうか?
卵のストックが少ない状況とは、一般に更年期に近づけば誰しも起こる状況なので、卵巣年齢が高いとされる低AMHの方には、更年期に起こりやすい血流不良があると考え、血流を改善し、規則正しい排卵を促す漢方婦人薬を使うことになります。
また、卵に質についてですが、抗酸化作用のある漢方薬が対応します。
卵は、主に酸化ストレスによって老化するといわれています。
酸化ストレスとは、呼吸により取り込んだ酸素の一部が悪さをして、身体を錆びさせていく事ですが、病気や老化の原因になることとが知られています。
卵の酸化ストレスは、生きてきた時間に比例するので、卵巣年齢が高くても、卵の質まではそれほど悪くない場合があります。
AMHが低くても、妊娠する方がいるのは、卵の量的な低下ほどに質的低下を免れていたの可能性があります。
卵のグレードと言う表現があり、各施設では様々な基準を設けて卵の質を評価していますが、遺伝情報である卵の染色体の質を判定しているわけではありません。卵の見た目が良く、見た目が良い方が妊娠率に良い結果を及ぼすという視点で、グレードを判定しているようです。
一方で、子宮の状態を整えることも大切です。
胚盤胞まで育ったので、子宮へ移植した時に、着床しないケースがあります。
この場合は、子宮内膜の状態をよくする漢方薬が応じます。
子宮は、子を育てるベッドのようなものです。胎児と母親は臍帯(へその緒)で結ばれますが、それは妊娠成立後、3か月程度経過してからです。受精卵と子宮は、着床後に先ずは血流で結ばれる必要があります。
血流改善を得意とする漢方薬では、子宮の状態をよくするために、卵巣年齢が高い方でも早い段階から使用します。
AMHが低く卵巣年齢が高いとされる方には
①血流を整え
②酸化ストレスを低減し
③子宮内膜の状態を改善する
というスタンスで、不妊症漢方療法をお使いいただいています。
2016年05月09日
湿度と排卵
湿度の高い時期は、漢方薬の保管に注意してほしいですね
特に粉薬や、煎じ薬は、防腐剤を含まないものが多く、粉薬ならば固まって飲みにくくなったり、煎じ薬(煎じた後の薬液)は傷みやすくなりますので、なるべく湿度を避けた保管をお願いしています。

外気の湿度が増してくることは、梅雨や秋雨の季節ならば当たり前ですが、湿度の多い環境で暮らすヒトも、その影響からは逃れられません。
冬の寒さで手先がかじかむのは、日常的に体感しますが、湿度が高い時期に、体の中が湿気るなんてことがあるのでしょうか?
漢方の世界では、体の湿気が増えるという概念があります。
不妊症漢方相談において、頻繁に遭遇する多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん:PCOS)があります。
このPCOSは、排卵の異常を認めますが、この病態を分析していくと湿盛(しっせい)と呼ばれる状態に行き着くケースがあります。
この湿盛、漢方の考えにおいて体の中の湿度が高い状態の事を指します。
PCOSならすべてのケースで湿盛なわけではなく、湿盛だからすべて排卵異常をきたす訳ではないのですが、ヒトは外界からの影響、こと妊活においても、温度や湿度などの影響を少なからず受けていると、漢方では考えています。

特に粉薬や、煎じ薬は、防腐剤を含まないものが多く、粉薬ならば固まって飲みにくくなったり、煎じ薬(煎じた後の薬液)は傷みやすくなりますので、なるべく湿度を避けた保管をお願いしています。


外気の湿度が増してくることは、梅雨や秋雨の季節ならば当たり前ですが、湿度の多い環境で暮らすヒトも、その影響からは逃れられません。
冬の寒さで手先がかじかむのは、日常的に体感しますが、湿度が高い時期に、体の中が湿気るなんてことがあるのでしょうか?
漢方の世界では、体の湿気が増えるという概念があります。
不妊症漢方相談において、頻繁に遭遇する多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん:PCOS)があります。
このPCOSは、排卵の異常を認めますが、この病態を分析していくと湿盛(しっせい)と呼ばれる状態に行き着くケースがあります。
この湿盛、漢方の考えにおいて体の中の湿度が高い状態の事を指します。
PCOSならすべてのケースで湿盛なわけではなく、湿盛だからすべて排卵異常をきたす訳ではないのですが、ヒトは外界からの影響、こと妊活においても、温度や湿度などの影響を少なからず受けていると、漢方では考えています。

2016年04月08日
初潮年齢と妊活漢方療法
以前、東洋医学の古典「黄帝内経」に、女性は7の倍数の年齢で体の変化が現れると解説しました。

黄帝内経では14歳で初潮が来るとしていますが、現在の日本人の初潮年齢は、全国調査で12歳程度と言われ、初潮が40年前と比べて約1歳ほど低年齢化していると報告されています。小児の発達加速現象の調査では、体格の向上を伴わず、初潮の低年齢化起きている事が明らかになっています。(発達加速現象の研究:阪大)
身長の伸びを伴わない初潮の低年齢化には、陰虚陽盛(いんきょようせい)の状態が考えられます。
陰虚陽盛とは、物質的な増大を伴わない機能亢進であり、身長の伸びを伴わない陰虚と、妊娠機能の早熟である陽盛が混在した状態です。
不妊症漢方相談においても、妊娠出産の適齢期にある女性たちが、発達加速現象を伴いながら思春期を過ごしてきた可能性を考慮しつつ、そこから現在の体質に至る過程を、詳細に観察していく必要がありそうです。

黄帝内経では14歳で初潮が来るとしていますが、現在の日本人の初潮年齢は、全国調査で12歳程度と言われ、初潮が40年前と比べて約1歳ほど低年齢化していると報告されています。小児の発達加速現象の調査では、体格の向上を伴わず、初潮の低年齢化起きている事が明らかになっています。(発達加速現象の研究:阪大)
身長の伸びを伴わない初潮の低年齢化には、陰虚陽盛(いんきょようせい)の状態が考えられます。
陰虚陽盛とは、物質的な増大を伴わない機能亢進であり、身長の伸びを伴わない陰虚と、妊娠機能の早熟である陽盛が混在した状態です。
不妊症漢方相談においても、妊娠出産の適齢期にある女性たちが、発達加速現象を伴いながら思春期を過ごしてきた可能性を考慮しつつ、そこから現在の体質に至る過程を、詳細に観察していく必要がありそうです。
2016年04月07日
女性は7の倍数で体に変化が起こる
「黄帝内経」という東洋医学の書物の中には女性は7の倍数で、身体に変化が現れると記されています。

妊娠に関連するところを抜粋すると
14歳で初潮し
21歳、28歳では腎気が盛んで、腎精がピークになり
35歳、42歳では腎気が衰退し、腎精が下り坂になり
49歳で閉経を迎える
※腎気とは妊娠・出産をつかさどる機能
※腎精とは妊娠・出産をつかさどる物質と置き換えるとイメージしやすいです。
黄帝内経が記されたとされるのは、中国前漢時代(紀元前206年~008年)です。
生活環境、栄養状態、初産年齢、出生数など大きく異なる現代においては、そのまま当てはまらないかもしれませんが、数百万年前とされる人類の歴史から見れば、およそ2200年の昔と現代が、大きく変わるとも言えないかもしれません。
7歳ごとに体の変化が起こるという黄帝内経の記述は、不妊症漢方治療における傾向を提示しています。
一般に、
腎気の盛んな28歳前後までは、排卵や月経のリズムを整える治療が中心です。
腎気が衰え始める35歳以降は、排卵のリズムを整えるだけでなく、年齢からくる腎精の不足を補うことが治療の中心になります。

妊娠に関連するところを抜粋すると
14歳で初潮し
21歳、28歳では腎気が盛んで、腎精がピークになり
35歳、42歳では腎気が衰退し、腎精が下り坂になり
49歳で閉経を迎える
※腎気とは妊娠・出産をつかさどる機能
※腎精とは妊娠・出産をつかさどる物質と置き換えるとイメージしやすいです。
黄帝内経が記されたとされるのは、中国前漢時代(紀元前206年~008年)です。
生活環境、栄養状態、初産年齢、出生数など大きく異なる現代においては、そのまま当てはまらないかもしれませんが、数百万年前とされる人類の歴史から見れば、およそ2200年の昔と現代が、大きく変わるとも言えないかもしれません。
7歳ごとに体の変化が起こるという黄帝内経の記述は、不妊症漢方治療における傾向を提示しています。
一般に、
腎気の盛んな28歳前後までは、排卵や月経のリズムを整える治療が中心です。
腎気が衰え始める35歳以降は、排卵のリズムを整えるだけでなく、年齢からくる腎精の不足を補うことが治療の中心になります。
2016年04月05日
規則正しい月経に肝腎なこと 排卵期編
排卵は、肝の発揚と腎の固摂のバランスによって制御されているとお話ししました。

教科書的には、
排卵期は、LHサージやエストロゲンサージと呼ばれるホルモン値の上昇の後、1~2日後に排卵が起こると考えられています。(不妊治療ガイダンス第3版 荒木重雄) などと説明されています。
ここで気になるのが、基礎体温の変化です。
基礎体温の上昇が1日でシャープに上昇することもあれば、4、5日かけて緩やかに上昇していくケースもあります。
シャープな基礎体温の上昇が得られれば、肝の発揚の力が強く、ゆっくりな上昇であれば、発揚の力が弱いと考えられます。
肝は木に属すとされ、肝の発揚とは、樹木が大地に根を張り養分を集め、太陽に向かって伸びやかに枝葉を伸ばしていく姿に重なります。
密生した木々が、われ先に光を求め、窮屈そうに背丈を伸ばしていくのとは違います。
肝の発揚に促された排卵は、女性の体が陰(低温相)から陽(高温相)に転化していくトリガーであり、不妊症漢方治療において、体質を判断する上で大切な要素です。
※基礎体温については別の機会にします

教科書的には、
排卵期は、LHサージやエストロゲンサージと呼ばれるホルモン値の上昇の後、1~2日後に排卵が起こると考えられています。(不妊治療ガイダンス第3版 荒木重雄) などと説明されています。
ここで気になるのが、基礎体温の変化です。
基礎体温の上昇が1日でシャープに上昇することもあれば、4、5日かけて緩やかに上昇していくケースもあります。
シャープな基礎体温の上昇が得られれば、肝の発揚の力が強く、ゆっくりな上昇であれば、発揚の力が弱いと考えられます。
肝は木に属すとされ、肝の発揚とは、樹木が大地に根を張り養分を集め、太陽に向かって伸びやかに枝葉を伸ばしていく姿に重なります。

密生した木々が、われ先に光を求め、窮屈そうに背丈を伸ばしていくのとは違います。

肝の発揚に促された排卵は、女性の体が陰(低温相)から陽(高温相)に転化していくトリガーであり、不妊症漢方治療において、体質を判断する上で大切な要素です。

※基礎体温については別の機会にします
2016年04月04日
規則正しい月経に肝腎なこと 排卵編
月経が規則正しく来るということは、妊活中において大切なことです
月経が起こる仕組みを理解するうえで、女性ホルモンや子宮内膜の状態、卵胞の大きさなどを知ることが大切です。
東洋医学において、月経の仕組みはどのように説明されるのでしょうか?今回は排卵編です。

排卵とは、卵胞の中に包蔵された卵子が、外向きの力によって外に押し出されることだと考えられています。
この作用の事を「肝の発揚」と言います。
一方で、東洋医学においては、卵胞の中で卵子の成長を促し、卵胞内にを留め置く内向きの力の存在を意識します。
この作用の事を「腎の固摂」と言います。
肝の発揚による外向き力を、腎の固摂による内向きの力で制御し、月経から約2週間かけて卵子を卵胞内にとどめ、5mm(月経初期)の卵胞を20mm前後(排卵直前)にまで成長させ、排卵に導いていきます。
ですから、排卵の乱れは、発揚と固摂の力関係が乱れた結果と解釈され、排卵が早かった、遅かった、無排卵であったなどと関連付けて、体質を判断していきます。

月経が起こる仕組みを理解するうえで、女性ホルモンや子宮内膜の状態、卵胞の大きさなどを知ることが大切です。
東洋医学において、月経の仕組みはどのように説明されるのでしょうか?今回は排卵編です。

排卵とは、卵胞の中に包蔵された卵子が、外向きの力によって外に押し出されることだと考えられています。
この作用の事を「肝の発揚」と言います。
一方で、東洋医学においては、卵胞の中で卵子の成長を促し、卵胞内にを留め置く内向きの力の存在を意識します。
この作用の事を「腎の固摂」と言います。
肝の発揚による外向き力を、腎の固摂による内向きの力で制御し、月経から約2週間かけて卵子を卵胞内にとどめ、5mm(月経初期)の卵胞を20mm前後(排卵直前)にまで成長させ、排卵に導いていきます。
ですから、排卵の乱れは、発揚と固摂の力関係が乱れた結果と解釈され、排卵が早かった、遅かった、無排卵であったなどと関連付けて、体質を判断していきます。
2016年04月02日
男性と女性では全く逆のこと
男性と女性は、同じ生き物ですが、妊活における解釈は全く逆です。

男性は、精子の元となる細胞から、細胞分裂によって成熟精子まで数を増やしていく必要があります。
女性は、産まれた後に卵の数が決まり、性成熟期から閉経までの間に、排卵をしていきます。
男性は0から増やし、女性は0に向かって減らしていきます。
また、精子は自力で泳いで動き回る一方、卵は自力で動くことはありません。
このような性質から、東洋医学において、男性は陽で、女性は陰に属するといわれます。
陰と陽で、性質が違うのですから、妊活サポートや不妊治療においても、男女で漢方治療の方向性は大きく異なります。
男性は、数を増やしていく事を、女性は、規則正しい排卵と、妊娠・出産・授乳を無事にこなせる体作りが、妊活中、不妊治療中から求められます。

男性は、精子の元となる細胞から、細胞分裂によって成熟精子まで数を増やしていく必要があります。
女性は、産まれた後に卵の数が決まり、性成熟期から閉経までの間に、排卵をしていきます。
男性は0から増やし、女性は0に向かって減らしていきます。
また、精子は自力で泳いで動き回る一方、卵は自力で動くことはありません。
このような性質から、東洋医学において、男性は陽で、女性は陰に属するといわれます。
陰と陽で、性質が違うのですから、妊活サポートや不妊治療においても、男女で漢方治療の方向性は大きく異なります。
男性は、数を増やしていく事を、女性は、規則正しい排卵と、妊娠・出産・授乳を無事にこなせる体作りが、妊活中、不妊治療中から求められます。