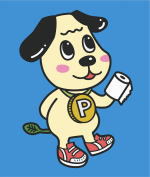2019年04月06日
デジタルデトックス?
先日、テレビを見ていたら
デジタルデトックスという言葉が耳に入りました。
気になったので調べてみると
デジタル機器(主にスマホ、他にはPCやテレビなども含む場合有り)から一定期間離れることだそうです。
スマホ疲れ、SNS疲れなど言われて久しいですね。
つながり過ぎる事による疲れ、処理できる以上の情報にさらされることによる疲れ、目や首肩などの疲れなどが起こるとされています。
これらの疲れは、運動した後に感じる心地よい疲れや、肉体疲労に伴う身体的な疲労とは違います。
動きを伴わない疲れですから、静的な疲労と言えそうです。

動けば元気を消耗して疲れるのは解りますが、動きが無いのも疲れる?となると困ったものですね。
東洋医学的な視点からは、この様な状態は、気の巡りの悪さが背景にあると理解できそうです。気滞(きたい)と呼ぶこともあります。
スマホやネットからの情報のインプットに偏り、心がパンクしてしまう、画面を凝視して筋肉のしなやかさが失われる、人とつながり過ぎて自分を抑え込みすぎてしまうことがありますね。
心身に渡る、この様な窮屈さは、気滞であり疲労のもとです。
気滞が疲労となるのは、気が伸びやかに全身を巡るものだという前提があるからです。
デジタル機器との付き合い方というのは、これからの時代の大きな課題となりそうですね。
今日もご愛読ありがとうございました(^_^.)
漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
いつまでも長引く不調がなかなか治らず、どこに相談してよいかわからない方
いつまでも健康で若々しくいたいと願う方
お気軽にご相談ください♪
ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
影山薬局は、あなたのかかりつけ相談薬局です
デジタルデトックスという言葉が耳に入りました。
気になったので調べてみると
デジタル機器(主にスマホ、他にはPCやテレビなども含む場合有り)から一定期間離れることだそうです。

スマホ疲れ、SNS疲れなど言われて久しいですね。

つながり過ぎる事による疲れ、処理できる以上の情報にさらされることによる疲れ、目や首肩などの疲れなどが起こるとされています。
これらの疲れは、運動した後に感じる心地よい疲れや、肉体疲労に伴う身体的な疲労とは違います。
動きを伴わない疲れですから、静的な疲労と言えそうです。

動けば元気を消耗して疲れるのは解りますが、動きが無いのも疲れる?となると困ったものですね。
東洋医学的な視点からは、この様な状態は、気の巡りの悪さが背景にあると理解できそうです。気滞(きたい)と呼ぶこともあります。
スマホやネットからの情報のインプットに偏り、心がパンクしてしまう、画面を凝視して筋肉のしなやかさが失われる、人とつながり過ぎて自分を抑え込みすぎてしまうことがありますね。
心身に渡る、この様な窮屈さは、気滞であり疲労のもとです。
気滞が疲労となるのは、気が伸びやかに全身を巡るものだという前提があるからです。
デジタル機器との付き合い方というのは、これからの時代の大きな課題となりそうですね。
今日もご愛読ありがとうございました(^_^.)
漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
いつまでも長引く不調がなかなか治らず、どこに相談してよいかわからない方
いつまでも健康で若々しくいたいと願う方
お気軽にご相談ください♪

ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
影山薬局は、あなたのかかりつけ相談薬局です
2017年12月13日
【薬剤師監修】漢方薬は体質に合えば、味や匂いが美味しく感じる?
漢方薬をこれから飲んでみようという方にとって、漢方薬の味や匂いについては気になる所ですね。
漢方薬の原料になる物が、生薬と呼ばれる薬草を中心にしたものですから、味や匂いの想像がつかないという方も少なくありません。
はじめて漢方薬を飲もうとする方から、
『漢方は体質に合っていれば、味や匂いは美味しく感じるのですか?』というお声を良く聞きます。漢方薬が体質に合っている時は、味や匂いは美味しく感じるという情報は、雑誌やテレビなどでも時々紹介されていますね。
私はそのように聞かれた場合
『体質に合っているかどうがと、漢方薬の味や匂いに関連はないですよ』とお答えしています。
その理由として
実際の漢方相談の現場では、漢方薬の味や匂いに否定的な方でも、漢方薬の効果をしっかり実感していることが多くあるからです。

漢方薬は、生薬と呼ばれる薬草が主な原料です。
もう少し具体的に説明すると
漢方薬の多くは、痛いとか痒いと言った直接的な症状に作用させているのではありません。
漢方薬は、漢方独特の考えに基づいて分類される体質(証;しょう)に対して処方されています。
その為、漢方薬が効いたという時は、服用した漢方薬が、自分の今の体質に合っていたと考えられます。
つまり、漢方薬が体質に合っている=漢方が効く となります。
次に、漢方薬が体質に合っている=漢方が効く=漢方薬を美味しく感じる になるか検証してみる必要があります。
ここでは割愛しますが、『漢方薬が体質に合っている=漢方が効く』を説明する際、漢方の理論の上で、その答えを理路整然と説明することが可能です。
一方で、『漢方が効く=漢方薬を美味しく感じる』へつながるかどうかは疑問が生じます。
その理由として4つを上げると
・漢方薬が効いた人ほど、漢方薬に対して肯定的な印象を持ちやすい。
・漢方薬で効果を得た人ほど服用の習慣がついており、習慣への親近感が高まることで、味や匂いと言った従属的な要素に寛容になる可能性がある。
・漢方薬の服用を続けるうちに、味そのものに慣れてしまっている。
・漢方薬は、冷えや痛みと言った主観的な症状への適応が多く、漢方薬で良い体感が得られれば、同じく味や匂いと言った主観的な要素へ、肯定的なイメージが波及しやすい可能性がある。
などが考えられます。
こういった偏りの事をバイアスと言います。
漢方薬が効いた人ほど、また、服用が長く習慣化されている人ほどバイアスがかかりやすく、味や匂いに肯定的に、あるいは美味しいという印象を持つ可能性を感じます。
実際に漢方相談をしていると
服用初期には味や匂いに否定的であっても、治療効果が上がってきたり、服用してからの期間経過が長くなるほど、味や匂いへの主観が大幅に改善することがよくあります。
これこそがバイアスで、本来は、漢方薬が効かなかった人へも同様に漢方薬の風味に関する調査して、それらを比較する必要があります。
ですが、漢方薬が効かなかった人に調査をするすべはありません。別の治療方法を試みてしまうからです。
以上の様に、『漢方薬が効く=漢方薬を美味しく感じる』とするには、かなりのバイアスがあり、ゆえに『漢方薬が体質に合っている=漢方薬が効く=漢方薬を美味しく感じる』とするにはかなりの無理を感じます。
漢方薬が効いたという人を母集団とする漢方薬の味や匂いへの肯定的な印象が、独り歩きしてしまっている可能性が高いのではないでしょうか?
では次に、『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が、どうして生まれてしまったのかについて考えてみたいと思います。
少し専門的な話になってしまいますが、漢方の理論の骨格となっている考えに、五行論と言われる理論があります。
五行論とは、かみ砕いていうと、身体の様々な働きや仕組みを、5つの要素に分けてとらえる理論です。
5つの要素の代表には五臓があり、身体の諸機能を、5つの臓に分類しています。(肝・心・脾・肺・腎)
五臓には、それぞれが好む味があるとされ、それらを五味(酸っぱい、苦い、甘い、辛い、塩からい)と言っています。
つまり、どこかの臓が調子を崩していれば、その臓が好む味を取り入れて回復させようという理屈がたちます。
漢方と同じ理論を共有する薬膳(食事をもって身体の失調を回復させる食養生のこと)では、この考えを重視します。
食事での養生において、美味しいと感じることは、回復を促したり治療効果を上げるうえでも大切な事は言うまでもありません。
すると、この考えが漢方治療の場面に水平展開されると、『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が出来上がってしまいます。先のバイアスを含めて、この辺りに『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が作り上げられた経緯があるのではないでしょうか。
最後に
漢方相談の現場では、実際に漢方薬の治療効果と、味や匂いの主観的な感想には、関連はありません。
中には、漢方薬の味や匂いが好きだとおっしゃる方もいますが、少数派です。
かと言って、漢方薬がとんでもなく不味いとか匂いがきついというわけではなく、ほとんどの人が風味に慣れて服用を続けています。
私個人としては、
『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる』と言う考えや感想があっても良いと思っています。
一方で『良薬口に苦し』を引き合いに、不味いからこそ効く気がするという様な、思い込みが治療効果を上げる事も少なくありません。
人の身体は、物質同士のやり取りだけで説明がつかない事が多く、様々な主観や客観が入り混じって心身に作用することで現状に落ち着いているはずです。
美味しいとか不味いと言った主観が入り込む要素が、漢方治療の場面にはあっても良いのではないでしょうか。
漢方らしさの現れとも言えるかもしれませんね。
今日もご愛読ありがとうございました(^_^.)
漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
いつまでも長引く不調がなかなか治らず、どこに相談してよいかわからない方
いつまでも健康で若々しくいたいと願う方
お気軽にご相談ください♪
ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
影山薬局は、あなたのかかりつけ相談薬局です
漢方薬の原料になる物が、生薬と呼ばれる薬草を中心にしたものですから、味や匂いの想像がつかないという方も少なくありません。
はじめて漢方薬を飲もうとする方から、
『漢方は体質に合っていれば、味や匂いは美味しく感じるのですか?』というお声を良く聞きます。漢方薬が体質に合っている時は、味や匂いは美味しく感じるという情報は、雑誌やテレビなどでも時々紹介されていますね。
私はそのように聞かれた場合
『体質に合っているかどうがと、漢方薬の味や匂いに関連はないですよ』とお答えしています。
その理由として
実際の漢方相談の現場では、漢方薬の味や匂いに否定的な方でも、漢方薬の効果をしっかり実感していることが多くあるからです。

漢方薬は、生薬と呼ばれる薬草が主な原料です。
もう少し具体的に説明すると
漢方薬の多くは、痛いとか痒いと言った直接的な症状に作用させているのではありません。
漢方薬は、漢方独特の考えに基づいて分類される体質(証;しょう)に対して処方されています。
その為、漢方薬が効いたという時は、服用した漢方薬が、自分の今の体質に合っていたと考えられます。
つまり、漢方薬が体質に合っている=漢方が効く となります。
次に、漢方薬が体質に合っている=漢方が効く=漢方薬を美味しく感じる になるか検証してみる必要があります。
ここでは割愛しますが、『漢方薬が体質に合っている=漢方が効く』を説明する際、漢方の理論の上で、その答えを理路整然と説明することが可能です。
一方で、『漢方が効く=漢方薬を美味しく感じる』へつながるかどうかは疑問が生じます。
その理由として4つを上げると
・漢方薬が効いた人ほど、漢方薬に対して肯定的な印象を持ちやすい。
・漢方薬で効果を得た人ほど服用の習慣がついており、習慣への親近感が高まることで、味や匂いと言った従属的な要素に寛容になる可能性がある。
・漢方薬の服用を続けるうちに、味そのものに慣れてしまっている。
・漢方薬は、冷えや痛みと言った主観的な症状への適応が多く、漢方薬で良い体感が得られれば、同じく味や匂いと言った主観的な要素へ、肯定的なイメージが波及しやすい可能性がある。
などが考えられます。
こういった偏りの事をバイアスと言います。
漢方薬が効いた人ほど、また、服用が長く習慣化されている人ほどバイアスがかかりやすく、味や匂いに肯定的に、あるいは美味しいという印象を持つ可能性を感じます。
実際に漢方相談をしていると
服用初期には味や匂いに否定的であっても、治療効果が上がってきたり、服用してからの期間経過が長くなるほど、味や匂いへの主観が大幅に改善することがよくあります。
これこそがバイアスで、本来は、漢方薬が効かなかった人へも同様に漢方薬の風味に関する調査して、それらを比較する必要があります。
ですが、漢方薬が効かなかった人に調査をするすべはありません。別の治療方法を試みてしまうからです。
以上の様に、『漢方薬が効く=漢方薬を美味しく感じる』とするには、かなりのバイアスがあり、ゆえに『漢方薬が体質に合っている=漢方薬が効く=漢方薬を美味しく感じる』とするにはかなりの無理を感じます。
漢方薬が効いたという人を母集団とする漢方薬の味や匂いへの肯定的な印象が、独り歩きしてしまっている可能性が高いのではないでしょうか?
では次に、『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が、どうして生まれてしまったのかについて考えてみたいと思います。
少し専門的な話になってしまいますが、漢方の理論の骨格となっている考えに、五行論と言われる理論があります。
五行論とは、かみ砕いていうと、身体の様々な働きや仕組みを、5つの要素に分けてとらえる理論です。
5つの要素の代表には五臓があり、身体の諸機能を、5つの臓に分類しています。(肝・心・脾・肺・腎)
五臓には、それぞれが好む味があるとされ、それらを五味(酸っぱい、苦い、甘い、辛い、塩からい)と言っています。
つまり、どこかの臓が調子を崩していれば、その臓が好む味を取り入れて回復させようという理屈がたちます。
漢方と同じ理論を共有する薬膳(食事をもって身体の失調を回復させる食養生のこと)では、この考えを重視します。
食事での養生において、美味しいと感じることは、回復を促したり治療効果を上げるうえでも大切な事は言うまでもありません。
すると、この考えが漢方治療の場面に水平展開されると、『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が出来上がってしまいます。先のバイアスを含めて、この辺りに『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる?』という理屈が作り上げられた経緯があるのではないでしょうか。
最後に
漢方相談の現場では、実際に漢方薬の治療効果と、味や匂いの主観的な感想には、関連はありません。
中には、漢方薬の味や匂いが好きだとおっしゃる方もいますが、少数派です。
かと言って、漢方薬がとんでもなく不味いとか匂いがきついというわけではなく、ほとんどの人が風味に慣れて服用を続けています。
私個人としては、
『漢方薬は体に合えば、味や匂いが美味しく感じる』と言う考えや感想があっても良いと思っています。
一方で『良薬口に苦し』を引き合いに、不味いからこそ効く気がするという様な、思い込みが治療効果を上げる事も少なくありません。
人の身体は、物質同士のやり取りだけで説明がつかない事が多く、様々な主観や客観が入り混じって心身に作用することで現状に落ち着いているはずです。
美味しいとか不味いと言った主観が入り込む要素が、漢方治療の場面にはあっても良いのではないでしょうか。
漢方らしさの現れとも言えるかもしれませんね。
今日もご愛読ありがとうございました(^_^.)
漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
いつまでも長引く不調がなかなか治らず、どこに相談してよいかわからない方
いつまでも健康で若々しくいたいと願う方
お気軽にご相談ください♪

ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
影山薬局は、あなたのかかりつけ相談薬局です
2016年07月30日
ヒトなぜ眠るのか? 不妊症編
いつもご愛読ありがとうございます。
富士市で不妊症の漢方相談20年、影山薬局 漢方薬剤師の影山です。
先日、大阪出張で、睡眠研究の世界的権威、筑波大学の裏出良博先生のお話を聞いてきました。
睡眠研究の権威ですから、なんとなく気難しい先生かと思いきや、優しい口調の穏やかな方でした。
あまりに穏やかな口調で、ついつい講義中の眠ってしまい したが、とても有意義なお話が聞けました。
したが、とても有意義なお話が聞けました。
冗談はさておき、講義の冒頭、睡眠研究の世界的権威のお口から
『なぜ眠るのか?それは解らない』 との告白があり、睡眠は、まだまだ研究途上でわからないことが沢山あるとのことです。
との告白があり、睡眠は、まだまだ研究途上でわからないことが沢山あるとのことです。
起きている時には、脳は様々な活動をしているのは、経験上何となくわかりますが、睡眠中の脳はどのような働きをしているのでしょう?
裏出先生によると
睡眠中は
1、脳・感覚機能の回復
2、成長ホルモンの分泌
3、脳内の老廃物を排泄
4、ストレスの緩和
5、免疫系の調節
6、記憶の定着、消去
を主に行っているとのことでした。
なるほど、、、と言われても、少し難しいですね、、、。
普段は、睡眠中にこのような働きを脳がしているということは、意識しないものです。

自分が良い睡眠がとれているか?質は問題ないか?を判断するのは難しいですが、睡眠が不足した時の、脳に現れる変化を知ると、睡眠が十分かどうかを判断する手掛かりになるかもしれません。
裏出先生のお話では、睡眠が不足すると現れやすい症状として
・判断力の低下→作業ミスが増える
・認知機能の低下→物忘れ、覚えられない
・ストレスがたまる→抑うつ状態
・免疫低下→風邪にかかりやすい、治らない
・食欲増進→甘味、塩味を好む→生活習慣病
・老廃物の蓄積→認知症
といった体の変化として現れやすくなるとのことでした。
これらの症状は、どれも妊活・不妊症治療中では、良くないことはわかります。
妊娠中や育児中に、この様な症状を訴える方は少なからずいますが、妊活中・不妊治療中においては、
日常ストレス+妊活ストレスなので、上記のような症状が現れるようなら、睡眠について考えてみる必要があるかもしれません。
『なぜ眠るのか?それは解らない』
脳医科学のトップランナー、裏出先生はそうおっしゃいますが、言葉にはできなくても、私たちの心や体は、なぜ眠るのかを知っています。
しっかり眠ること、これをもう一度じっくり考えていきましょう。
次回以降では、眠り方について取り上げていきます

漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
卵巣年齢が高い方、治療のステップアップを考えている方
不妊治療に行き詰っている、少しでも早く結果を出したい方
お気軽にご相談ください♪
ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
お二人にもかけがえのない幸せが訪れますように
富士市で不妊症の漢方相談20年、影山薬局 漢方薬剤師の影山です。
先日、大阪出張で、睡眠研究の世界的権威、筑波大学の裏出良博先生のお話を聞いてきました。
睡眠研究の権威ですから、なんとなく気難しい先生かと思いきや、優しい口調の穏やかな方でした。
あまりに穏やかな口調で、
 したが、とても有意義なお話が聞けました。
したが、とても有意義なお話が聞けました。
冗談はさておき、講義の冒頭、睡眠研究の世界的権威のお口から
『なぜ眠るのか?それは解らない』
 との告白があり、睡眠は、まだまだ研究途上でわからないことが沢山あるとのことです。
との告白があり、睡眠は、まだまだ研究途上でわからないことが沢山あるとのことです。起きている時には、脳は様々な活動をしているのは、経験上何となくわかりますが、睡眠中の脳はどのような働きをしているのでしょう?
裏出先生によると
睡眠中は
1、脳・感覚機能の回復
2、成長ホルモンの分泌
3、脳内の老廃物を排泄
4、ストレスの緩和
5、免疫系の調節
6、記憶の定着、消去
を主に行っているとのことでした。
なるほど、、、と言われても、少し難しいですね、、、。

普段は、睡眠中にこのような働きを脳がしているということは、意識しないものです。

自分が良い睡眠がとれているか?質は問題ないか?を判断するのは難しいですが、睡眠が不足した時の、脳に現れる変化を知ると、睡眠が十分かどうかを判断する手掛かりになるかもしれません。
裏出先生のお話では、睡眠が不足すると現れやすい症状として
・判断力の低下→作業ミスが増える
・認知機能の低下→物忘れ、覚えられない
・ストレスがたまる→抑うつ状態
・免疫低下→風邪にかかりやすい、治らない
・食欲増進→甘味、塩味を好む→生活習慣病
・老廃物の蓄積→認知症
といった体の変化として現れやすくなるとのことでした。

これらの症状は、どれも妊活・不妊症治療中では、良くないことはわかります。
妊娠中や育児中に、この様な症状を訴える方は少なからずいますが、妊活中・不妊治療中においては、
日常ストレス+妊活ストレスなので、上記のような症状が現れるようなら、睡眠について考えてみる必要があるかもしれません。
『なぜ眠るのか?それは解らない』
脳医科学のトップランナー、裏出先生はそうおっしゃいますが、言葉にはできなくても、私たちの心や体は、なぜ眠るのかを知っています。
しっかり眠ること、これをもう一度じっくり考えていきましょう。
次回以降では、眠り方について取り上げていきます


漢方薬で体質を整え、妊娠しやすい体作りを目指したい
卵巣年齢が高い方、治療のステップアップを考えている方
不妊治療に行き詰っている、少しでも早く結果を出したい方
お気軽にご相談ください♪

ホームページはhttp://kageyama-kusuri.jp/index.html ←こちらからどうぞ
メール又は電話0545-63-3150までご連絡ください。
お二人にもかけがえのない幸せが訪れますように
2016年07月18日
女神さまの漢方薬
漢方薬のネーミングは面白いものがあります。
女神散と言う漢方薬は、ネーミングからして女性的ですが、
この処方、江戸から明治の漢方大家:浅田宗伯(あさだそうはく)が残したと言われています。
(めがみさん)と読みたいところですが、(にょしんさん)と読むのが正解です。
女性特有の神経症を治す漢方薬で、産前産後の神経症、更年期障害、月経不順などの効能が知られています。
不妊症漢方相談でも、時々使われています。
浅田宗伯は、徳川将軍家お抱えの漢方医でしたが、その弟子が浅田氏のもとで飴を作り、今日、浅田飴として伝わっていますね。

浅田飴と女伸散は、おなじ浅田氏を由来としているとは、、、最近、浅田飴のCMをされていた永六輔さんが他界されたときに、ふと思い出していました。
女神散と言う漢方薬は、ネーミングからして女性的ですが、
この処方、江戸から明治の漢方大家:浅田宗伯(あさだそうはく)が残したと言われています。
(めがみさん)と読みたいところですが、(にょしんさん)と読むのが正解です。
女性特有の神経症を治す漢方薬で、産前産後の神経症、更年期障害、月経不順などの効能が知られています。
不妊症漢方相談でも、時々使われています。
浅田宗伯は、徳川将軍家お抱えの漢方医でしたが、その弟子が浅田氏のもとで飴を作り、今日、浅田飴として伝わっていますね。

浅田飴と女伸散は、おなじ浅田氏を由来としているとは、、、最近、浅田飴のCMをされていた永六輔さんが他界されたときに、ふと思い出していました。
2016年07月14日
ABC妊活
先日、不妊の漢方相談時に、タレントの川村ひかるさん(36歳)が妊娠されたということが話題になりました。
川村さんは、20代で子宮内膜症、30代で若年性の更年期障害になり、ホルモンが少なく妊娠しにくい体ということを自覚されていたとの事。
そこで、普段の生活習慣をしっかり整えるよう生活されていたそうで、
『A当たり前のことを/Bバカにせず/Cちゃんとする』を意識していたとのことです。
この頭文字をとってABC妊活と名付けて実践していたようで
1時間でも多く睡眠を取る
脳をリラックスさせるため夜にスマホやPCを見ない、
家の電気をダウンライトにする
冷たい飲み物を控える 、など体に刺激を与えるものをできるだけ控えていたそうです。
、など体に刺激を与えるものをできるだけ控えていたそうです。
ネーミングも覚えやすくて良いのですが、内容がとても良いですね。
とくに、不妊当事者であり、実践されて結果を出している方の体験は、重みがあります。
東洋医学では、養生を大切にしますが、不妊症の方、妊活中の方は、治療だけでなく、周囲からの期待やプレッシャーがストレスとなります。
同じ一年を過ごすのであっても、妊娠を意識する1年と、そうでない1年では、ストレスレベルが違います。
だからこそ、養生をしてほしいと思います。

東洋医学では、妊活中の睡眠不足は絶対にNGです。
妊活中は、疲れをとるために寝るのではなく、妊娠をつかさどる腎気を養うために、積極的に眠ってほしいです。
育児中の二人目不妊では、睡眠不足をどう解消するかがとても大切。
なかなか睡眠時間の確保は意識しないと難しいですね、でも寝ることを第一優先にすると、忙しい日常の中でも睡眠時間は造れたりするものです。
睡眠の初期は、大量の成長ホルモンが出ますね。工夫してみてほしいです。
川村さんは、20代で子宮内膜症、30代で若年性の更年期障害になり、ホルモンが少なく妊娠しにくい体ということを自覚されていたとの事。
そこで、普段の生活習慣をしっかり整えるよう生活されていたそうで、
『A当たり前のことを/Bバカにせず/Cちゃんとする』を意識していたとのことです。
この頭文字をとってABC妊活と名付けて実践していたようで
1時間でも多く睡眠を取る

脳をリラックスさせるため夜にスマホやPCを見ない、

家の電気をダウンライトにする

冷たい飲み物を控える
 、など体に刺激を与えるものをできるだけ控えていたそうです。
、など体に刺激を与えるものをできるだけ控えていたそうです。ネーミングも覚えやすくて良いのですが、内容がとても良いですね。
とくに、不妊当事者であり、実践されて結果を出している方の体験は、重みがあります。
東洋医学では、養生を大切にしますが、不妊症の方、妊活中の方は、治療だけでなく、周囲からの期待やプレッシャーがストレスとなります。
同じ一年を過ごすのであっても、妊娠を意識する1年と、そうでない1年では、ストレスレベルが違います。
だからこそ、養生をしてほしいと思います。

東洋医学では、妊活中の睡眠不足は絶対にNGです。
妊活中は、疲れをとるために寝るのではなく、妊娠をつかさどる腎気を養うために、積極的に眠ってほしいです。
育児中の二人目不妊では、睡眠不足をどう解消するかがとても大切。
なかなか睡眠時間の確保は意識しないと難しいですね、でも寝ることを第一優先にすると、忙しい日常の中でも睡眠時間は造れたりするものです。
睡眠の初期は、大量の成長ホルモンが出ますね。工夫してみてほしいです。
2016年05月25日
恋しい夫よ 当帰(とうき)
不妊症漢方療法に使われる漢方薬の中には、当帰(とうき)と言う薬草がよく使われます。
当帰は婦人の聖薬と言われ、血を増やし、良く巡らせる働きがあるとされています。

存在感のある独特な香りがしますが、不思議と穏やかな気分になります
十中九帰と言われ、不妊症を含めた婦人病には、10の処方のうち9は当帰が入ります。
この当帰、名前の由来が面白いのです。
仲の良かった1組の夫婦、妻が病弱で里帰りして療養することに。
悩んだ妻は、知人から教えてもらった薬草を飲み続けました。
すると元気を取り戻し、夫の元へ帰ることができ、
『恋しい夫よ、当(まさ)に我が家に帰るべし』と言ったことから、その名が付いたとか。
その時に婦人が飲んでいたのが、当帰と言うわけです。
他にも諸説あるようですが、いずれの説も、妻が体調を回復して、夫婦仲が良くなるという点で共通しており、当帰が婦人の良薬として認識されていたことがうかがえます。
ある病気でお悩みのご婦人と話をしたときに、そんな当帰にまつわるエピソードをお話ししたことを思い出しました
当帰は婦人の聖薬と言われ、血を増やし、良く巡らせる働きがあるとされています。


存在感のある独特な香りがしますが、不思議と穏やかな気分になります

十中九帰と言われ、不妊症を含めた婦人病には、10の処方のうち9は当帰が入ります。
この当帰、名前の由来が面白いのです。
仲の良かった1組の夫婦、妻が病弱で里帰りして療養することに。
悩んだ妻は、知人から教えてもらった薬草を飲み続けました。
すると元気を取り戻し、夫の元へ帰ることができ、
『恋しい夫よ、当(まさ)に我が家に帰るべし』と言ったことから、その名が付いたとか。
その時に婦人が飲んでいたのが、当帰と言うわけです。
他にも諸説あるようですが、いずれの説も、妻が体調を回復して、夫婦仲が良くなるという点で共通しており、当帰が婦人の良薬として認識されていたことがうかがえます。
ある病気でお悩みのご婦人と話をしたときに、そんな当帰にまつわるエピソードをお話ししたことを思い出しました