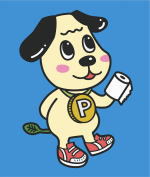2018年06月15日
【夏の養生】季節の陰陽と個の陰陽
蒸し暑いのが日本の夏の特養です
夏は外気温が高く、外気が私たちの活動の元となる熱を提供し、活動量が増えてきます(陽の増大)
また、活動を下支えする燃料、つまり飲食物やそれに伴う排泄といった物質の流出入が盛んになります(陰の増大)
簡単に言えば、気温が上がって代謝が活発になり、活動量や飲食の量が増えている様子を表しています。
これは、個の陰陽が夏の影響を受けて大きくなっている様子です。
一方で、夏の陰陽とは、気温が高い(陽)事と、湿気や雨が多い(陰)事で、他の季節に比べて蒸し暑い様子を表しています。
夏の陰陽が個の陰陽に影響を及ぼします。その逆はありません。私たち個がどれほど頑張っても、夏が暑いことには変わりはありません。夏(季節)が主で、個が従という主従関係に有ります。

夏の陰陽の盛衰が、個の陰陽に影響を与える。
漢方生活における陰陽の理想は、季節の陰陽と個の陰陽が同調することです。
夏の暑さで活動量が増え、よく食べてよく出して活発に過ごせたらいいですね。
ところが実際にはそう上手くはいかないのが現実です。
夏の陰陽が極まり過ぎると、猛烈な暑さが続いたり、長雨や豪雨が私たちの生活を脅かすことも最近少なくありません。
夏の陰陽の増大が、暴走するかのような事がよく起こります。
こういう激しい季節の時は、私たち個の陰陽も影響を受けます。
個の陽が急に極まれば熱中症で倒れるかもしれません。陰が極まれば多汗や下痢が続くことも考えられます。いずれも消耗しますね。季節の陰陽が増大する夏によくみられる症状です。
住環境を整えるでも、生活習慣を改めるにしても、夏の陰陽の影響を一方的に受けていることを根本に考える必要がありそうです。
まとめ
個の陰陽は、季節の陰陽の影響を一方的に受ける

夏は外気温が高く、外気が私たちの活動の元となる熱を提供し、活動量が増えてきます(陽の増大)
また、活動を下支えする燃料、つまり飲食物やそれに伴う排泄といった物質の流出入が盛んになります(陰の増大)
簡単に言えば、気温が上がって代謝が活発になり、活動量や飲食の量が増えている様子を表しています。
これは、個の陰陽が夏の影響を受けて大きくなっている様子です。
一方で、夏の陰陽とは、気温が高い(陽)事と、湿気や雨が多い(陰)事で、他の季節に比べて蒸し暑い様子を表しています。
夏の陰陽が個の陰陽に影響を及ぼします。その逆はありません。私たち個がどれほど頑張っても、夏が暑いことには変わりはありません。夏(季節)が主で、個が従という主従関係に有ります。

夏の陰陽の盛衰が、個の陰陽に影響を与える。
漢方生活における陰陽の理想は、季節の陰陽と個の陰陽が同調することです。
夏の暑さで活動量が増え、よく食べてよく出して活発に過ごせたらいいですね。
ところが実際にはそう上手くはいかないのが現実です。
夏の陰陽が極まり過ぎると、猛烈な暑さが続いたり、長雨や豪雨が私たちの生活を脅かすことも最近少なくありません。
夏の陰陽の増大が、暴走するかのような事がよく起こります。
こういう激しい季節の時は、私たち個の陰陽も影響を受けます。
個の陽が急に極まれば熱中症で倒れるかもしれません。陰が極まれば多汗や下痢が続くことも考えられます。いずれも消耗しますね。季節の陰陽が増大する夏によくみられる症状です。
住環境を整えるでも、生活習慣を改めるにしても、夏の陰陽の影響を一方的に受けていることを根本に考える必要がありそうです。
まとめ
個の陰陽は、季節の陰陽の影響を一方的に受ける
タグ :陰陽
2018年05月31日
【夏の養生】陰陽の増大について
夏の性格を漢方生活の視点で見ると
『陰陽が増大する季節』と言うことが出来るとお話ししました。
詳しくはこちらの記事が参考になります。
今回は、改めて夏の陰陽の増大について、私たちの身体を例にあげて考えてみましょう。
夏になって気温が上がってくるという事は、自然環境や生活環境から、活動の原資となる熱の支援を受ける事を意味しています。
熱ければ熱いほど良いというのではありませんが、一般に、外気の熱による支援を受ければ、寒くて動きの悪い季節より身体が動くようになるのです。これが『夏は陰陽が増大する季節』の陽(活動)が増えていく様子を表してます。
一方で、活動量が増えればお腹が減り、自然と食事が増えてきますね。飲水も増え、その分、汗や尿も増えて、身体の外から取り入れるものと出ていくものの流通量が増えていきます。食べ物や水分と言った物の流通量が増えていく事が自然です。これは、活動の物質的側面である陰の増大を意味しています。
陰陽の増大とは、活動量が増えて、それを支える飲食物の量や、排泄の量が増えていく様子になります。
日長がのびて暖かくなる事を通じて、活動量や生理的な現象が活発になる様子でもありますね。

私たちの身体の陰陽が、この様に、程よい加減を保ちながら増大していけば順調と言えそうですが、実際には夏バテが心配であったり、夏に調子を崩す方は少なくありません。
それは、夏は『陰陽が増大する季節』ですが、必ずしも一本調子で増大するのではない 事がひとつ原因として考えられます。
事がひとつ原因として考えられます。
夏の熱さ(陽)と湿気(陰)は
初夏から梅雨のころまでは、暑さよりも湿気が勝る傾向があります。陰盛(陰が盛ん)
梅雨明けから夏の盛りの頃までは、気温の高さが際立ちます。陽盛(陽が盛ん)
晩夏の頃になると、暑さも湿気も不安定で、過ごしやすくなる一方で残暑や前線、台風などの影響を受け、夏らしい雰囲気が終わります。
この様に、夏の陰陽が盛衰していく様子が一本調子ではないことが解ります。
これだけ外部の環境が変化してくのですから、そこから大きな影響を受ける事を考えると、夏をやり過ごすのは容易ではないと言えます。
まとめ
夏の陰陽の増大は一本調子ではない
『陰陽が増大する季節』と言うことが出来るとお話ししました。
詳しくはこちらの記事が参考になります。
今回は、改めて夏の陰陽の増大について、私たちの身体を例にあげて考えてみましょう。
夏になって気温が上がってくるという事は、自然環境や生活環境から、活動の原資となる熱の支援を受ける事を意味しています。
熱ければ熱いほど良いというのではありませんが、一般に、外気の熱による支援を受ければ、寒くて動きの悪い季節より身体が動くようになるのです。これが『夏は陰陽が増大する季節』の陽(活動)が増えていく様子を表してます。
一方で、活動量が増えればお腹が減り、自然と食事が増えてきますね。飲水も増え、その分、汗や尿も増えて、身体の外から取り入れるものと出ていくものの流通量が増えていきます。食べ物や水分と言った物の流通量が増えていく事が自然です。これは、活動の物質的側面である陰の増大を意味しています。
陰陽の増大とは、活動量が増えて、それを支える飲食物の量や、排泄の量が増えていく様子になります。
日長がのびて暖かくなる事を通じて、活動量や生理的な現象が活発になる様子でもありますね。

私たちの身体の陰陽が、この様に、程よい加減を保ちながら増大していけば順調と言えそうですが、実際には夏バテが心配であったり、夏に調子を崩す方は少なくありません。
それは、夏は『陰陽が増大する季節』ですが、必ずしも一本調子で増大するのではない
 事がひとつ原因として考えられます。
事がひとつ原因として考えられます。夏の熱さ(陽)と湿気(陰)は
初夏から梅雨のころまでは、暑さよりも湿気が勝る傾向があります。陰盛(陰が盛ん)
梅雨明けから夏の盛りの頃までは、気温の高さが際立ちます。陽盛(陽が盛ん)
晩夏の頃になると、暑さも湿気も不安定で、過ごしやすくなる一方で残暑や前線、台風などの影響を受け、夏らしい雰囲気が終わります。
この様に、夏の陰陽が盛衰していく様子が一本調子ではないことが解ります。
これだけ外部の環境が変化してくのですから、そこから大きな影響を受ける事を考えると、夏をやり過ごすのは容易ではないと言えます。
まとめ
夏の陰陽の増大は一本調子ではない
2018年05月14日
【夏の養生】夏の性格について
最近は季節の変わり目がはっきりしませんね。
特に季節の変わり目では寒暖差が大きくなったり、気象が安定しないなど、健康管理に気を使います。夏は、春に続く季節ですから、春→夏の順です。
春の性格である『外向き』の様子から、夏の傾向を徐々に強めていくのが季節の移り変わりです。
春の性格につていは 、こちら の記事が参考になります。
今回は、夏の傾向とは一体どのようなものなのかを、漢方生活の視点で考えていきましょう。
その前に、春についてのもう一度、簡単におさらいをしてみる必要があります。
それは、季節は個の存在ではなく、四季の流れの中で、折々の傾向を発展衰退させながら変化していくものだからです。
あらためて、春の特徴を簡単に言うと
①春は色々なものが動き出す季節
②その動きは外向きである
③外向きの根拠は熱にある
という事でした。熱というエネルギーを根拠にして、色々なものが外向きに動き出す様子でしたね。
これを、外向きに広がる様子や、動きが活発な様子から 陽的である、と言い換えることが出来そうです。
陽的とは陰的の対義語で、内向きでノロノロとした様子ではなく、外向きで活発な様子をイメージしてもらえればいいです。
陽的な春の傾向を引き継ぐ形で夏に向かっていきますが、熱や外向きの動きの傾向は、夏も引き続き際限なく拡大していくかというとそうではありませんね。植物が夏枯れしたり、私たちにも夏バテや暑気あたりという言葉がある様に、陽的な傾向はどこかで頭打ちとなり失速します。
そこに、夏の傾向を紐解くヒントがありそうです。
夏枯れや夏バテを考えてみますと、草勢の盛んな草木が日照りにあって枯死したり、夏バテにおいては食欲不振などの胃腸障害を伴う事が少なくありません。
これらに共通する事は、活動、つまり陽的な働きに対して、水分や栄養といった陰的根拠が同調できなくなって起こる失調と言えます。
例えて言えば、補給をせずに走り続けた結果、ガス欠を起こしてしまったような状態です。
また、春の活動は、冬の陰的充足を背景になされますが、夏は冬の蓄えはすでに無く、陽的(活動)増大とともに陰的欠乏(燃料切れ)を起こしやすいと言えるかもしれません。
このような事から、漢方生活の視点において
『夏は、陰陽が増大する季節』と言うことが出来そうです。

夏はますます暑くなりますから、陽的根拠である熱は加給されることになります。一方で、動きを維持するための陰的根拠も加給され同調する季節です。雨がよく降って植物が良く育つという事でしょうか。私たちの身体においては、個の陰陽の失調が病気の発露となるため、養生が大切になります。
ただ、夏至における日長ピークと暑さのピークのずれ、雨季の到来(梅雨)、四季における陽的ピークからの衰退の始まりなど、初夏、仲夏、晩夏にそれぞれ特徴や趣きがあります。
それらについては、個別に考えていく必要がありそうです。
まとめ
夏は陰陽が増大する季節

特に季節の変わり目では寒暖差が大きくなったり、気象が安定しないなど、健康管理に気を使います。夏は、春に続く季節ですから、春→夏の順です。
春の性格である『外向き』の様子から、夏の傾向を徐々に強めていくのが季節の移り変わりです。
春の性格につていは 、こちら の記事が参考になります。
今回は、夏の傾向とは一体どのようなものなのかを、漢方生活の視点で考えていきましょう。
その前に、春についてのもう一度、簡単におさらいをしてみる必要があります。
それは、季節は個の存在ではなく、四季の流れの中で、折々の傾向を発展衰退させながら変化していくものだからです。
あらためて、春の特徴を簡単に言うと
①春は色々なものが動き出す季節
②その動きは外向きである
③外向きの根拠は熱にある
という事でした。熱というエネルギーを根拠にして、色々なものが外向きに動き出す様子でしたね。
これを、外向きに広がる様子や、動きが活発な様子から 陽的である、と言い換えることが出来そうです。
陽的とは陰的の対義語で、内向きでノロノロとした様子ではなく、外向きで活発な様子をイメージしてもらえればいいです。
陽的な春の傾向を引き継ぐ形で夏に向かっていきますが、熱や外向きの動きの傾向は、夏も引き続き際限なく拡大していくかというとそうではありませんね。植物が夏枯れしたり、私たちにも夏バテや暑気あたりという言葉がある様に、陽的な傾向はどこかで頭打ちとなり失速します。
そこに、夏の傾向を紐解くヒントがありそうです。
夏枯れや夏バテを考えてみますと、草勢の盛んな草木が日照りにあって枯死したり、夏バテにおいては食欲不振などの胃腸障害を伴う事が少なくありません。
これらに共通する事は、活動、つまり陽的な働きに対して、水分や栄養といった陰的根拠が同調できなくなって起こる失調と言えます。

例えて言えば、補給をせずに走り続けた結果、ガス欠を起こしてしまったような状態です。
また、春の活動は、冬の陰的充足を背景になされますが、夏は冬の蓄えはすでに無く、陽的(活動)増大とともに陰的欠乏(燃料切れ)を起こしやすいと言えるかもしれません。
このような事から、漢方生活の視点において
『夏は、陰陽が増大する季節』と言うことが出来そうです。

夏はますます暑くなりますから、陽的根拠である熱は加給されることになります。一方で、動きを維持するための陰的根拠も加給され同調する季節です。雨がよく降って植物が良く育つという事でしょうか。私たちの身体においては、個の陰陽の失調が病気の発露となるため、養生が大切になります。
ただ、夏至における日長ピークと暑さのピークのずれ、雨季の到来(梅雨)、四季における陽的ピークからの衰退の始まりなど、初夏、仲夏、晩夏にそれぞれ特徴や趣きがあります。
それらについては、個別に考えていく必要がありそうです。
まとめ
夏は陰陽が増大する季節