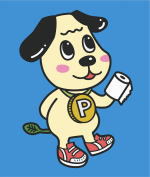2018年05月31日
【夏の養生】陰陽の増大について
夏の性格を漢方生活の視点で見ると
『陰陽が増大する季節』と言うことが出来るとお話ししました。
詳しくはこちらの記事が参考になります。
今回は、改めて夏の陰陽の増大について、私たちの身体を例にあげて考えてみましょう。
夏になって気温が上がってくるという事は、自然環境や生活環境から、活動の原資となる熱の支援を受ける事を意味しています。
熱ければ熱いほど良いというのではありませんが、一般に、外気の熱による支援を受ければ、寒くて動きの悪い季節より身体が動くようになるのです。これが『夏は陰陽が増大する季節』の陽(活動)が増えていく様子を表してます。
一方で、活動量が増えればお腹が減り、自然と食事が増えてきますね。飲水も増え、その分、汗や尿も増えて、身体の外から取り入れるものと出ていくものの流通量が増えていきます。食べ物や水分と言った物の流通量が増えていく事が自然です。これは、活動の物質的側面である陰の増大を意味しています。
陰陽の増大とは、活動量が増えて、それを支える飲食物の量や、排泄の量が増えていく様子になります。
日長がのびて暖かくなる事を通じて、活動量や生理的な現象が活発になる様子でもありますね。

私たちの身体の陰陽が、この様に、程よい加減を保ちながら増大していけば順調と言えそうですが、実際には夏バテが心配であったり、夏に調子を崩す方は少なくありません。
それは、夏は『陰陽が増大する季節』ですが、必ずしも一本調子で増大するのではない 事がひとつ原因として考えられます。
事がひとつ原因として考えられます。
夏の熱さ(陽)と湿気(陰)は
初夏から梅雨のころまでは、暑さよりも湿気が勝る傾向があります。陰盛(陰が盛ん)
梅雨明けから夏の盛りの頃までは、気温の高さが際立ちます。陽盛(陽が盛ん)
晩夏の頃になると、暑さも湿気も不安定で、過ごしやすくなる一方で残暑や前線、台風などの影響を受け、夏らしい雰囲気が終わります。
この様に、夏の陰陽が盛衰していく様子が一本調子ではないことが解ります。
これだけ外部の環境が変化してくのですから、そこから大きな影響を受ける事を考えると、夏をやり過ごすのは容易ではないと言えます。
まとめ
夏の陰陽の増大は一本調子ではない
『陰陽が増大する季節』と言うことが出来るとお話ししました。
詳しくはこちらの記事が参考になります。
今回は、改めて夏の陰陽の増大について、私たちの身体を例にあげて考えてみましょう。
夏になって気温が上がってくるという事は、自然環境や生活環境から、活動の原資となる熱の支援を受ける事を意味しています。
熱ければ熱いほど良いというのではありませんが、一般に、外気の熱による支援を受ければ、寒くて動きの悪い季節より身体が動くようになるのです。これが『夏は陰陽が増大する季節』の陽(活動)が増えていく様子を表してます。
一方で、活動量が増えればお腹が減り、自然と食事が増えてきますね。飲水も増え、その分、汗や尿も増えて、身体の外から取り入れるものと出ていくものの流通量が増えていきます。食べ物や水分と言った物の流通量が増えていく事が自然です。これは、活動の物質的側面である陰の増大を意味しています。
陰陽の増大とは、活動量が増えて、それを支える飲食物の量や、排泄の量が増えていく様子になります。
日長がのびて暖かくなる事を通じて、活動量や生理的な現象が活発になる様子でもありますね。

私たちの身体の陰陽が、この様に、程よい加減を保ちながら増大していけば順調と言えそうですが、実際には夏バテが心配であったり、夏に調子を崩す方は少なくありません。
それは、夏は『陰陽が増大する季節』ですが、必ずしも一本調子で増大するのではない
 事がひとつ原因として考えられます。
事がひとつ原因として考えられます。夏の熱さ(陽)と湿気(陰)は
初夏から梅雨のころまでは、暑さよりも湿気が勝る傾向があります。陰盛(陰が盛ん)
梅雨明けから夏の盛りの頃までは、気温の高さが際立ちます。陽盛(陽が盛ん)
晩夏の頃になると、暑さも湿気も不安定で、過ごしやすくなる一方で残暑や前線、台風などの影響を受け、夏らしい雰囲気が終わります。
この様に、夏の陰陽が盛衰していく様子が一本調子ではないことが解ります。
これだけ外部の環境が変化してくのですから、そこから大きな影響を受ける事を考えると、夏をやり過ごすのは容易ではないと言えます。
まとめ
夏の陰陽の増大は一本調子ではない
2018年05月14日
【夏の養生】夏の性格について
最近は季節の変わり目がはっきりしませんね。
特に季節の変わり目では寒暖差が大きくなったり、気象が安定しないなど、健康管理に気を使います。夏は、春に続く季節ですから、春→夏の順です。
春の性格である『外向き』の様子から、夏の傾向を徐々に強めていくのが季節の移り変わりです。
春の性格につていは 、こちら の記事が参考になります。
今回は、夏の傾向とは一体どのようなものなのかを、漢方生活の視点で考えていきましょう。
その前に、春についてのもう一度、簡単におさらいをしてみる必要があります。
それは、季節は個の存在ではなく、四季の流れの中で、折々の傾向を発展衰退させながら変化していくものだからです。
あらためて、春の特徴を簡単に言うと
①春は色々なものが動き出す季節
②その動きは外向きである
③外向きの根拠は熱にある
という事でした。熱というエネルギーを根拠にして、色々なものが外向きに動き出す様子でしたね。
これを、外向きに広がる様子や、動きが活発な様子から 陽的である、と言い換えることが出来そうです。
陽的とは陰的の対義語で、内向きでノロノロとした様子ではなく、外向きで活発な様子をイメージしてもらえればいいです。
陽的な春の傾向を引き継ぐ形で夏に向かっていきますが、熱や外向きの動きの傾向は、夏も引き続き際限なく拡大していくかというとそうではありませんね。植物が夏枯れしたり、私たちにも夏バテや暑気あたりという言葉がある様に、陽的な傾向はどこかで頭打ちとなり失速します。
そこに、夏の傾向を紐解くヒントがありそうです。
夏枯れや夏バテを考えてみますと、草勢の盛んな草木が日照りにあって枯死したり、夏バテにおいては食欲不振などの胃腸障害を伴う事が少なくありません。
これらに共通する事は、活動、つまり陽的な働きに対して、水分や栄養といった陰的根拠が同調できなくなって起こる失調と言えます。
例えて言えば、補給をせずに走り続けた結果、ガス欠を起こしてしまったような状態です。
また、春の活動は、冬の陰的充足を背景になされますが、夏は冬の蓄えはすでに無く、陽的(活動)増大とともに陰的欠乏(燃料切れ)を起こしやすいと言えるかもしれません。
このような事から、漢方生活の視点において
『夏は、陰陽が増大する季節』と言うことが出来そうです。

夏はますます暑くなりますから、陽的根拠である熱は加給されることになります。一方で、動きを維持するための陰的根拠も加給され同調する季節です。雨がよく降って植物が良く育つという事でしょうか。私たちの身体においては、個の陰陽の失調が病気の発露となるため、養生が大切になります。
ただ、夏至における日長ピークと暑さのピークのずれ、雨季の到来(梅雨)、四季における陽的ピークからの衰退の始まりなど、初夏、仲夏、晩夏にそれぞれ特徴や趣きがあります。
それらについては、個別に考えていく必要がありそうです。
まとめ
夏は陰陽が増大する季節

特に季節の変わり目では寒暖差が大きくなったり、気象が安定しないなど、健康管理に気を使います。夏は、春に続く季節ですから、春→夏の順です。
春の性格である『外向き』の様子から、夏の傾向を徐々に強めていくのが季節の移り変わりです。
春の性格につていは 、こちら の記事が参考になります。
今回は、夏の傾向とは一体どのようなものなのかを、漢方生活の視点で考えていきましょう。
その前に、春についてのもう一度、簡単におさらいをしてみる必要があります。
それは、季節は個の存在ではなく、四季の流れの中で、折々の傾向を発展衰退させながら変化していくものだからです。
あらためて、春の特徴を簡単に言うと
①春は色々なものが動き出す季節
②その動きは外向きである
③外向きの根拠は熱にある
という事でした。熱というエネルギーを根拠にして、色々なものが外向きに動き出す様子でしたね。
これを、外向きに広がる様子や、動きが活発な様子から 陽的である、と言い換えることが出来そうです。
陽的とは陰的の対義語で、内向きでノロノロとした様子ではなく、外向きで活発な様子をイメージしてもらえればいいです。
陽的な春の傾向を引き継ぐ形で夏に向かっていきますが、熱や外向きの動きの傾向は、夏も引き続き際限なく拡大していくかというとそうではありませんね。植物が夏枯れしたり、私たちにも夏バテや暑気あたりという言葉がある様に、陽的な傾向はどこかで頭打ちとなり失速します。
そこに、夏の傾向を紐解くヒントがありそうです。
夏枯れや夏バテを考えてみますと、草勢の盛んな草木が日照りにあって枯死したり、夏バテにおいては食欲不振などの胃腸障害を伴う事が少なくありません。
これらに共通する事は、活動、つまり陽的な働きに対して、水分や栄養といった陰的根拠が同調できなくなって起こる失調と言えます。

例えて言えば、補給をせずに走り続けた結果、ガス欠を起こしてしまったような状態です。
また、春の活動は、冬の陰的充足を背景になされますが、夏は冬の蓄えはすでに無く、陽的(活動)増大とともに陰的欠乏(燃料切れ)を起こしやすいと言えるかもしれません。
このような事から、漢方生活の視点において
『夏は、陰陽が増大する季節』と言うことが出来そうです。

夏はますます暑くなりますから、陽的根拠である熱は加給されることになります。一方で、動きを維持するための陰的根拠も加給され同調する季節です。雨がよく降って植物が良く育つという事でしょうか。私たちの身体においては、個の陰陽の失調が病気の発露となるため、養生が大切になります。
ただ、夏至における日長ピークと暑さのピークのずれ、雨季の到来(梅雨)、四季における陽的ピークからの衰退の始まりなど、初夏、仲夏、晩夏にそれぞれ特徴や趣きがあります。
それらについては、個別に考えていく必要がありそうです。
まとめ
夏は陰陽が増大する季節
2018年02月21日
【漢方生活のススメ】物も人も変化している
物も人も変化しています。
物も人も互いに変化しながら手を取り合って暮らしが成り立っています。人間関係も同じです。互いに変化しあう者同士が寄せ集まって暮らし、日々、様々な現象を作り出しています。
まるで、人とお付き合いするかのような視点で、物と向き合う時、どのような気付きが得られるでしょうか?
今回は、物も人も変化しているとはどういうことか?漢方生活の視点を通じて考えてみましょう。
物の変化
物には物体としての陰的側面と、それがもたらす機能という陽的側面があります。
物の変化は、この陰陽両面にわたって起こる変化です。
物の経年変化は必ず起こります。色があせたり擦り減ったりしていく事は、物を使う使わないにかかわらず起こることです。
元々はバラバラの物質が集まって一つの物になっているので、元のバラバラな状態に戻ろうとする変化は自然な事です。
物の経年変化に伴い、物の陽的側面である機能が変化します。
包丁の切れ味が落ちたり、スマホの機能が陳腐化いくように、機能も経年的に変化していきます。
私達は、物の陰陽とつながることで、日々を暮らしていますが、つながる対象となる物は、陰的にも陽的にも変化をしているものだと考えるのが漢方生活です。
つながる対象は変化してます。ところが、私達も変化をしていることを忘れてはいけません。
私達の変化とはどういう事でしょうか?
人の変化
人の変化といっても様々ありますので、物と同じように人を陰的要素と陽的要素に分けて考えてみましょう。
人を陰陽に分けようとする時、様々な切り口があります。一般的に、身体的要素と精神的要素に分類することがあります。簡単に言えば心と身体という事になるでしょうか。
人を陰陽に分けて考える事は、あくまでも変化に気づくための視点の提供が主で、分ける事は言葉の上でのみ成立する便宜的な意味合いしかありません。
ここでは、身体を陰、心を陽とします。

人の身体の変化、つまり陰的変化は様々です。生・長・壮・老・已(せい・ちょう・そろ・ろう・い)など、人の身体の変化を表す表現があります。簡単に言えば、生まれてから成長して安定し、やがて老いて終末を迎える大まかな流れの事です。その途中では、身体の成長や老衰もあれば病気や怪我もあり、陰的変化は概ね放物線を描きながらも紆余曲折します。
次に、人の心の変化、つまり陽的変化はどのように経過するのでしょう?
陽的な変化は、全方位的な変化の可能性があり、その経過は無限と言えるかもしれません。ただし、陽的変化は、陰的変化(身体的変化)と共にある事と、環境からの影響を受ける事から、ある程度の方向性は見いだせるかもしれません。
簡単ではありますが、この様に、人も陰的、陽的な側面において大きく変化をしている様子が分かります。
変化しあう同士がつながる
物も変化してる、人も変化しているという事ですが、そのつながりは、柱と柱をボルトで締め付ける様な堅牢なものではありません。
適当な言葉が見つかりませんが、物と人とのつながりの強さは、柔軟性のあるものだと言えるかもしれません。物と人とのつながりは、物と人の変化の上に成り立つもので、意図的に強めたり弱めたりと作用できるものではありません。
物と人のそれぞれの陰陽に渡る変化の中で、それらのつながりも、強まったり弱まったりしながら刻々と変化している様子がうかがえます。
まとめ
物だけでなく人も陰陽両面において変化している。
それらのつながりは、それぞれの陰陽変化のなかで強まったり弱まったりと変化している。

物も人も互いに変化しながら手を取り合って暮らしが成り立っています。人間関係も同じです。互いに変化しあう者同士が寄せ集まって暮らし、日々、様々な現象を作り出しています。
まるで、人とお付き合いするかのような視点で、物と向き合う時、どのような気付きが得られるでしょうか?
今回は、物も人も変化しているとはどういうことか?漢方生活の視点を通じて考えてみましょう。
物の変化
物には物体としての陰的側面と、それがもたらす機能という陽的側面があります。
物の変化は、この陰陽両面にわたって起こる変化です。
物の経年変化は必ず起こります。色があせたり擦り減ったりしていく事は、物を使う使わないにかかわらず起こることです。
元々はバラバラの物質が集まって一つの物になっているので、元のバラバラな状態に戻ろうとする変化は自然な事です。
物の経年変化に伴い、物の陽的側面である機能が変化します。
包丁の切れ味が落ちたり、スマホの機能が陳腐化いくように、機能も経年的に変化していきます。
私達は、物の陰陽とつながることで、日々を暮らしていますが、つながる対象となる物は、陰的にも陽的にも変化をしているものだと考えるのが漢方生活です。

つながる対象は変化してます。ところが、私達も変化をしていることを忘れてはいけません。
私達の変化とはどういう事でしょうか?
人の変化
人の変化といっても様々ありますので、物と同じように人を陰的要素と陽的要素に分けて考えてみましょう。
人を陰陽に分けようとする時、様々な切り口があります。一般的に、身体的要素と精神的要素に分類することがあります。簡単に言えば心と身体という事になるでしょうか。
人を陰陽に分けて考える事は、あくまでも変化に気づくための視点の提供が主で、分ける事は言葉の上でのみ成立する便宜的な意味合いしかありません。
ここでは、身体を陰、心を陽とします。

人の身体の変化、つまり陰的変化は様々です。生・長・壮・老・已(せい・ちょう・そろ・ろう・い)など、人の身体の変化を表す表現があります。簡単に言えば、生まれてから成長して安定し、やがて老いて終末を迎える大まかな流れの事です。その途中では、身体の成長や老衰もあれば病気や怪我もあり、陰的変化は概ね放物線を描きながらも紆余曲折します。
次に、人の心の変化、つまり陽的変化はどのように経過するのでしょう?
陽的な変化は、全方位的な変化の可能性があり、その経過は無限と言えるかもしれません。ただし、陽的変化は、陰的変化(身体的変化)と共にある事と、環境からの影響を受ける事から、ある程度の方向性は見いだせるかもしれません。
簡単ではありますが、この様に、人も陰的、陽的な側面において大きく変化をしている様子が分かります。
変化しあう同士がつながる
物も変化してる、人も変化しているという事ですが、そのつながりは、柱と柱をボルトで締め付ける様な堅牢なものではありません。
適当な言葉が見つかりませんが、物と人とのつながりの強さは、柔軟性のあるものだと言えるかもしれません。物と人とのつながりは、物と人の変化の上に成り立つもので、意図的に強めたり弱めたりと作用できるものではありません。
物と人のそれぞれの陰陽に渡る変化の中で、それらのつながりも、強まったり弱まったりしながら刻々と変化している様子がうかがえます。
まとめ
物だけでなく人も陰陽両面において変化している。
それらのつながりは、それぞれの陰陽変化のなかで強まったり弱まったりと変化している。
2018年02月13日
【漢方生活のススメ】物を大切にする
昔から、物を大切に扱いなさいだとか、物を粗末に扱ってはいけない、などと言います。その背景には、世代や時代ごとに様々な価値観があって良いと思いますが、漢方生活の視点では、どのような考え方が出来るのでしょうか?
今回は、物を大切にすることを、漢方生活の視点を通じて考えてみましょう。
漢方生活においては、物を持つことは、物の陰陽とつながる事です。

簡単に言えば、物の、物体としての側面(陰)と、その物がもたらす機能的側面(陽)とつながることです。私たちの暮らしにおいて、物の陰陽とつながることで、物が人に活かされ、人も物に活かされる関係が有ります。
陰陽は不可分です。物が壊れたり、捨てたり紛失したような場合、私たちと物の陰陽とのつながりが絶たれてしまいます。すると、物が人に活かされ、人も物に活かされる関係もなくなります。
物を持つことの意味について詳しく>>>こちらの記事
この様に考えると、私たちの暮らしは、物と相互の依存関係に有ると言えます。
ここで一つ補足です。
人が物に活かされるというのは、物を通じて人の暮らしが豊かになったり便利になったりすることです。
一方で、物が人に活かされるというのはどういう事でしょう?
それは、物の持つ機能が充分に発揮されることです。物の、本来とは違った新たな活用法が見つかれば、それも物を活かす事につながります。
この様な、暮らしにおける物との相互の依存関係において、人と物との力量バランスが生じてくるのは仕方がありません。
物があまりに高機能すぎて使いこなせない場合もあれば、シンプル過ぎて使い物にならないなどという事は少なくありません。サイズや形が合わないなども、力量バランスの不一致と言えます。
物が人に合わせてオーダーメイドに作られているわけではありませんので、これはこれで仕方のない事なのかもしれませんね。いずれにしても、人も物も活き活きとしているとは言い難いですね。
物と人の力量を近づける
物と人の力量を近づける事で、物が人に活かされ、人が物に活かされる関係が持続します。いわゆる 『しっくりくる』 と言える関係です。しっくりくる関係において、物は自然と大切に扱われる事になります。これが、漢方生活における物を大切にすることの本質になります。言い換えれば、物を大切にするとは、物との『しっくりくる関係づくり』をすることです。しっくりこない物は粗雑に扱っていいのではありません。しっくりくる物だけを大切にするのでもありません。
物とのしっくりくる関係を作り上げていく暮らしの中に、物を大切に扱う姿があります。
丁寧に扱う、きれいに扱う、優しく扱う、大事に使うなども、言葉の上では 物を大切にする と大差はありません。ところが、物と人との相互の依存関係を理解し、物とのバランスの取れた良好な関係づくりを背景にすると、物との付き合い方も一味違ったふうに見えて来るのではないでしょうか?
まとめ
物と人との相互の依存関係を理解し、物とのバランスの取れた良好な関係づくりの中に、物を大切に扱う姿勢が見出される
今回は、物を大切にすることを、漢方生活の視点を通じて考えてみましょう。

漢方生活においては、物を持つことは、物の陰陽とつながる事です。

簡単に言えば、物の、物体としての側面(陰)と、その物がもたらす機能的側面(陽)とつながることです。私たちの暮らしにおいて、物の陰陽とつながることで、物が人に活かされ、人も物に活かされる関係が有ります。
陰陽は不可分です。物が壊れたり、捨てたり紛失したような場合、私たちと物の陰陽とのつながりが絶たれてしまいます。すると、物が人に活かされ、人も物に活かされる関係もなくなります。
物を持つことの意味について詳しく>>>こちらの記事
この様に考えると、私たちの暮らしは、物と相互の依存関係に有ると言えます。
ここで一つ補足です。
人が物に活かされるというのは、物を通じて人の暮らしが豊かになったり便利になったりすることです。
一方で、物が人に活かされるというのはどういう事でしょう?
それは、物の持つ機能が充分に発揮されることです。物の、本来とは違った新たな活用法が見つかれば、それも物を活かす事につながります。
この様な、暮らしにおける物との相互の依存関係において、人と物との力量バランスが生じてくるのは仕方がありません。
物があまりに高機能すぎて使いこなせない場合もあれば、シンプル過ぎて使い物にならないなどという事は少なくありません。サイズや形が合わないなども、力量バランスの不一致と言えます。
物が人に合わせてオーダーメイドに作られているわけではありませんので、これはこれで仕方のない事なのかもしれませんね。いずれにしても、人も物も活き活きとしているとは言い難いですね。
物と人の力量を近づける
物と人の力量を近づける事で、物が人に活かされ、人が物に活かされる関係が持続します。いわゆる 『しっくりくる』 と言える関係です。しっくりくる関係において、物は自然と大切に扱われる事になります。これが、漢方生活における物を大切にすることの本質になります。言い換えれば、物を大切にするとは、物との『しっくりくる関係づくり』をすることです。しっくりこない物は粗雑に扱っていいのではありません。しっくりくる物だけを大切にするのでもありません。
物とのしっくりくる関係を作り上げていく暮らしの中に、物を大切に扱う姿があります。
丁寧に扱う、きれいに扱う、優しく扱う、大事に使うなども、言葉の上では 物を大切にする と大差はありません。ところが、物と人との相互の依存関係を理解し、物とのバランスの取れた良好な関係づくりを背景にすると、物との付き合い方も一味違ったふうに見えて来るのではないでしょうか?
まとめ
物と人との相互の依存関係を理解し、物とのバランスの取れた良好な関係づくりの中に、物を大切に扱う姿勢が見出される
タグ :物を大切にする
2018年02月03日
【漢方生活のススメ】物を持つことの意味
普段は、物を持つことの意味について考えることなど無いかもしれません。
物が余るほどある時代に、一つ一つの物に、所有する意味を問うことは不可能かもしれませんね。例え同じ物であっても、もつ状況や時代によって、その意味は無限に見出せるかもしれませんが、限りなくあるという事は無いに等しいとも言えます。
今回は、物を所有することの意味について、漢方生活における原則的な考え方をご紹介します。原則的な視点を持つことで、物との付き合い方を再考するヒントになればと思います。
物の中に陰陽を見る
私達は、物に囲まれて生活しています。もし、それらの物が一瞬にして目の前からなくなってしまったらどうなるでしょう?
携帯電話、車、家、冷蔵庫、、、、一つでもなくなってしまったら生活が成り立たなくなるかもしれませんね。物があるというのは有り難いことです。
一方で、物はなくなっても、物が持つ機能だけが残れば、物そのものがなくても困ることはありません。
ところが、物そのものと、それが持つ機能を切り離すことはできません。物と機能はセットになっているからです。
ですから、私たちは、物に囲まれた生活をしていると言えますが、一方で、機能に囲まれた生活をしているとも言えます。
陰陽とは、 【事物をあらゆる視点で陰と陽の2つに分けてとらえる視点】の事です。
すると、物の中に陰陽を見出そうとする時、実体のある『物そのもの』が陰、それがもたらす機能(役割)を陽とすることが出来ます。
陰陽は不可分です。
使われない物は機能や役割が発揮されず、ただの物体です。壊れて機能しなくなった物、役割を終えた物も物体です。物体には陰陽はありません。陰陽が切り離されてしまえば、通常は不要になってしまいます。
つまり、私達が物を持つという事は、物の陰陽とつながる事です。

物の陰陽とつながることで、物が人に活かされ、人も物に活かされるバランスが出来上がります。
このバランスをとるのが難しいのですね。オーバースペックや寸足らず、、、ベストバランスというのが在るわけでありません。
ただ、すでに長い付き合いとなっている物ほど、良好なバランスを築けているのかもしれませんね。
人と、物の陰陽とがつながっているという視点を持つことで、物の扱い方や、物との付き合い方のヒントになるかもしれません。
まとめ
人は、物の陰陽とつながっている。
物が余るほどある時代に、一つ一つの物に、所有する意味を問うことは不可能かもしれませんね。例え同じ物であっても、もつ状況や時代によって、その意味は無限に見出せるかもしれませんが、限りなくあるという事は無いに等しいとも言えます。
今回は、物を所有することの意味について、漢方生活における原則的な考え方をご紹介します。原則的な視点を持つことで、物との付き合い方を再考するヒントになればと思います。

物の中に陰陽を見る
私達は、物に囲まれて生活しています。もし、それらの物が一瞬にして目の前からなくなってしまったらどうなるでしょう?
携帯電話、車、家、冷蔵庫、、、、一つでもなくなってしまったら生活が成り立たなくなるかもしれませんね。物があるというのは有り難いことです。
一方で、物はなくなっても、物が持つ機能だけが残れば、物そのものがなくても困ることはありません。
ところが、物そのものと、それが持つ機能を切り離すことはできません。物と機能はセットになっているからです。
ですから、私たちは、物に囲まれた生活をしていると言えますが、一方で、機能に囲まれた生活をしているとも言えます。
陰陽とは、 【事物をあらゆる視点で陰と陽の2つに分けてとらえる視点】の事です。
すると、物の中に陰陽を見出そうとする時、実体のある『物そのもの』が陰、それがもたらす機能(役割)を陽とすることが出来ます。
陰陽は不可分です。
使われない物は機能や役割が発揮されず、ただの物体です。壊れて機能しなくなった物、役割を終えた物も物体です。物体には陰陽はありません。陰陽が切り離されてしまえば、通常は不要になってしまいます。
つまり、私達が物を持つという事は、物の陰陽とつながる事です。

物の陰陽とつながることで、物が人に活かされ、人も物に活かされるバランスが出来上がります。
このバランスをとるのが難しいのですね。オーバースペックや寸足らず、、、ベストバランスというのが在るわけでありません。
ただ、すでに長い付き合いとなっている物ほど、良好なバランスを築けているのかもしれませんね。

人と、物の陰陽とがつながっているという視点を持つことで、物の扱い方や、物との付き合い方のヒントになるかもしれません。
まとめ
人は、物の陰陽とつながっている。
タグ :物を持つ意味
2018年01月31日
【漢方生活のススメ】物の減らすときの考え方
物を減らすときの考え方を切り口に、物の本質について考えてみましょう。
所有する物を減らそうと考える時、減らしたことで得られるメリットやデメリットがあります。
メリットやデメリットは、個々人の置かれた状況によりそれぞれ異なるため、ある人にとってのメリットが、別の人にとってデメリットであると言う様な矛盾が生じます。タイミングによっても、随分変わってしまうでしょう。当然それらを扱う事には普遍的な意義はありません。物に対して行動する動機付けになることはあっても、物を減らす(又は増やす)事に対する本質的な答えとは成りえません。
漢方生活ではむしろ、物を減らす(又は増やす)事による本質的な意味を理解することが大切と考えます。
個々人の置かれた状況ごとにその本質と照らし合わせることで、暮らしに沿った物との付き合い方を考える基準が出来れば良いですね。
今回は、物を減らす(又は増やす)ことの、本質的な意味を考えてみましょう。その為に、物の本質と私たちの関わりについて3つの視点を紹介します。
①物は巡る
物の本質は、巡る性質を持っている事です。物は、いつかに人工的であれ自然的であれ形作られて現存しています。元はバラバラの物が寄せ集まって一つの物を成していますが、それはやがて元のバラバラに戻っていく流れがあります。最終的には土にかえるという広い意味において、物は巡っていると言えます。
もう少し狭い意味において、例えば私たちの所有するものについても同様です。
いつかのタイミングで家に持ち込まれた物は、早かれ遅かれ必ず家の外に出ていく事になります。どんなに大切にしている物であっても、所有者不在となれば、何らかの形で処分されることになるでしょう。
より日常的な話をすれば、買った物を消費して捨てる、壊れて捨てる、他人に譲るなど、巡る性質があることが解ります。
これらを一言い換えれば、物を所有し続ける事は不可能だという事です。
②物には気配りが必要
物を所有すれば、そのものに対して気配りが必要となります。物には、先に述べた巡る性質があるためです。

簡単に言えば、物を維持管理するのに気を使うという事になりなります。高価で価値の高い物には、その扱いに細心の注意を払います。ゴミの様に不要なものであっても、カビや異臭がないか注意する必要があります。このようなわかりやすい例に限らず、全ての所有物には気配りが紐づいていると漢方生活では考えます。
それぞれは日常的に気づかないほどの小さな気配りかもしれませんが、物と気配りはセットになっています。
③気配りの二面性
気配りをすることで、心地良く感じることもあれば、それを疎ましく感じる事もあります。実は、この気配りには二面性があります。
花を飾ったらきれいだなと心地良く思う一方で、手入れや片付けが面倒だなと感じる事があります。大切なコレクションに囲まれて過ごす時間は幸せですが、それを失う不安が同居しています。心地良さと疎ましさは一定ではなく、どちらが際立っているかは、物・人・事・自分などあらゆる関わり合いとのバランスの中で揺れ動いています。どのバランスが良いという話ではありません。仕事が忙しくなれば物への気配りを疎ましく感じます。病気をしてもそうです。
気配りの二面性は、周囲からのあらゆる影響を受けて揺れ動くという認識を持つと良いです。物との付き合い方を、物対人ではなく、全方位的な視点をもって考える時に大切な考えです。
ここまで、物の本質と私たちの関わりについて3つの視点を紹介してきました。
これらの事は、暮らしに沿った物との付き合い方を考えるうえでのヒントになるかもしれません。いつもこのような考えを意識して暮らす必要はありませんが、物を減らしたり増やしたりする時、あるいは自然と減ってきた、増えてきたといった、変化の節目に思い出すだけで十分です。
物を通じて暮らしを見直す際の手助けになれば良いですね。
まとめ
物には巡る性質があり、それを維持管理するために気配りが紐づいています。気配りには二面性があり、それは暮らしのあらゆる事物からの影響を受けて変化しています。

所有する物を減らそうと考える時、減らしたことで得られるメリットやデメリットがあります。

メリットやデメリットは、個々人の置かれた状況によりそれぞれ異なるため、ある人にとってのメリットが、別の人にとってデメリットであると言う様な矛盾が生じます。タイミングによっても、随分変わってしまうでしょう。当然それらを扱う事には普遍的な意義はありません。物に対して行動する動機付けになることはあっても、物を減らす(又は増やす)事に対する本質的な答えとは成りえません。
漢方生活ではむしろ、物を減らす(又は増やす)事による本質的な意味を理解することが大切と考えます。
個々人の置かれた状況ごとにその本質と照らし合わせることで、暮らしに沿った物との付き合い方を考える基準が出来れば良いですね。
今回は、物を減らす(又は増やす)ことの、本質的な意味を考えてみましょう。その為に、物の本質と私たちの関わりについて3つの視点を紹介します。
①物は巡る
物の本質は、巡る性質を持っている事です。物は、いつかに人工的であれ自然的であれ形作られて現存しています。元はバラバラの物が寄せ集まって一つの物を成していますが、それはやがて元のバラバラに戻っていく流れがあります。最終的には土にかえるという広い意味において、物は巡っていると言えます。
もう少し狭い意味において、例えば私たちの所有するものについても同様です。
いつかのタイミングで家に持ち込まれた物は、早かれ遅かれ必ず家の外に出ていく事になります。どんなに大切にしている物であっても、所有者不在となれば、何らかの形で処分されることになるでしょう。
より日常的な話をすれば、買った物を消費して捨てる、壊れて捨てる、他人に譲るなど、巡る性質があることが解ります。
これらを一言い換えれば、物を所有し続ける事は不可能だという事です。
②物には気配りが必要
物を所有すれば、そのものに対して気配りが必要となります。物には、先に述べた巡る性質があるためです。

簡単に言えば、物を維持管理するのに気を使うという事になりなります。高価で価値の高い物には、その扱いに細心の注意を払います。ゴミの様に不要なものであっても、カビや異臭がないか注意する必要があります。このようなわかりやすい例に限らず、全ての所有物には気配りが紐づいていると漢方生活では考えます。
それぞれは日常的に気づかないほどの小さな気配りかもしれませんが、物と気配りはセットになっています。
③気配りの二面性
気配りをすることで、心地良く感じることもあれば、それを疎ましく感じる事もあります。実は、この気配りには二面性があります。
花を飾ったらきれいだなと心地良く思う一方で、手入れや片付けが面倒だなと感じる事があります。大切なコレクションに囲まれて過ごす時間は幸せですが、それを失う不安が同居しています。心地良さと疎ましさは一定ではなく、どちらが際立っているかは、物・人・事・自分などあらゆる関わり合いとのバランスの中で揺れ動いています。どのバランスが良いという話ではありません。仕事が忙しくなれば物への気配りを疎ましく感じます。病気をしてもそうです。
気配りの二面性は、周囲からのあらゆる影響を受けて揺れ動くという認識を持つと良いです。物との付き合い方を、物対人ではなく、全方位的な視点をもって考える時に大切な考えです。
ここまで、物の本質と私たちの関わりについて3つの視点を紹介してきました。
これらの事は、暮らしに沿った物との付き合い方を考えるうえでのヒントになるかもしれません。いつもこのような考えを意識して暮らす必要はありませんが、物を減らしたり増やしたりする時、あるいは自然と減ってきた、増えてきたといった、変化の節目に思い出すだけで十分です。
物を通じて暮らしを見直す際の手助けになれば良いですね。
まとめ
物には巡る性質があり、それを維持管理するために気配りが紐づいています。気配りには二面性があり、それは暮らしのあらゆる事物からの影響を受けて変化しています。
タグ :物の減らし方
2018年01月18日
【漢方生活のススメ】内外の物のつながり
ここまで、所有する物の性質を、漢方生活の視点でみてきました。
所有物は、必要性と心地良さを切り口にした視点で、4つのカテゴリに分けられ、いずれかのカテゴリに分類されます。
所有する物のカテゴリ分けについて詳しい記事は>>こちら
現在所有する物は、どこかのタイミングで家の中に持ち込まれ、いずれかのタイミングで出ていく事になります。
今回は、 家に入ってくる、あるいは出ていく物の流れと、所有する物の流れとの関連について考えていきます。
物の流れには、家の中に入ってくる物として補(必要な物)や外邪(必要でない物)があり、不要で家の外へ捨てられていく捨がありましたね。入り口は補と外邪、出口は捨という事になります。

捨・補・外邪について詳しい記事は>>>こちら
これらの物の内外の流れを一つにまとめると、このような図になります。

ここで、内の流れとは所有物のカテゴリ移動、外の流れとは物の出入りを意味しています。
内の流れも外の流れも、必要性という同じ軸を持っていますが、物が家の中に入って所有されると、心地良さという情緒的な要素が新たな軸に加わります。物が家の中に入ったり出ていったりする際には必要性という軸があり、物を所有し続けるかどうかは、必要性だけでなく、心地良さの軸が加わると考えます。
物が入ってくる際にも、必要性だけでなく心地良さの判断軸を取り入れても良いと思います。漢方生活の視点では、物がもたらす心地良さの真価や多様性は、物を所有して初めて明らかになると考えるため、物が入ってくる段階(補や外邪)では、簡潔に必要性の一軸としいます。
同様に、物を捨てる捨の段階では、物の心地良さと所有者は分断されるため、やはり簡潔に必要性の一軸としています。
このようにして、物の内外の流れが明らかになりました。
内と外は、流れとして一つにつながるはずです。漢方生活の視点で物流を見直すことで、物が滞留しやすい場所を把握し、所有物のバランスを見直すことが出来ます。
まとめ
物の出入りは必要性の、物の所有には必要性と心地良さの判断軸がある。
所有物は、必要性と心地良さを切り口にした視点で、4つのカテゴリに分けられ、いずれかのカテゴリに分類されます。
所有する物のカテゴリ分けについて詳しい記事は>>こちら
現在所有する物は、どこかのタイミングで家の中に持ち込まれ、いずれかのタイミングで出ていく事になります。
今回は、 家に入ってくる、あるいは出ていく物の流れと、所有する物の流れとの関連について考えていきます。
物の流れには、家の中に入ってくる物として補(必要な物)や外邪(必要でない物)があり、不要で家の外へ捨てられていく捨がありましたね。入り口は補と外邪、出口は捨という事になります。

捨・補・外邪について詳しい記事は>>>こちら
これらの物の内外の流れを一つにまとめると、このような図になります。

ここで、内の流れとは所有物のカテゴリ移動、外の流れとは物の出入りを意味しています。
内の流れも外の流れも、必要性という同じ軸を持っていますが、物が家の中に入って所有されると、心地良さという情緒的な要素が新たな軸に加わります。物が家の中に入ったり出ていったりする際には必要性という軸があり、物を所有し続けるかどうかは、必要性だけでなく、心地良さの軸が加わると考えます。
物が入ってくる際にも、必要性だけでなく心地良さの判断軸を取り入れても良いと思います。漢方生活の視点では、物がもたらす心地良さの真価や多様性は、物を所有して初めて明らかになると考えるため、物が入ってくる段階(補や外邪)では、簡潔に必要性の一軸としいます。
同様に、物を捨てる捨の段階では、物の心地良さと所有者は分断されるため、やはり簡潔に必要性の一軸としています。
このようにして、物の内外の流れが明らかになりました。
内と外は、流れとして一つにつながるはずです。漢方生活の視点で物流を見直すことで、物が滞留しやすい場所を把握し、所有物のバランスを見直すことが出来ます。
まとめ
物の出入りは必要性の、物の所有には必要性と心地良さの判断軸がある。
タグ :漢方生活のススメ
2018年01月12日
【漢方生活のススメ】所有する物の性質
所有する物には、必要性と心地良さの2つの軸を切り口にした、4つのカテゴリがある事をお伝えしました。
必要性や心地良さについては、明確な線引きが出来るものではないかもしれません。あるいは、個々人によって異なって良いものですから、無理やりに所有する物をカテゴリ分けする必要もありません。何となくフワっと物の持つ顔付きをとらえる視点として利用すれば良いですね。
所有する物の4つのカテゴリ分けに関する記事は>>>こちら
この様に、所有する物についてアバウトなとらえ方をするには理由があります。今回はその理由を考えながら物が持つ性質を漢方生活流に考えていきましょう。
漢方生活では、物は巡る性質を持つと考えます。これは、漢方生活の骨格をなす東洋医学の考えが元にあります。東洋医学では、体の中に取り込んだ物は、巡ることによってその機能を発揮する とされています。巡らなければタダの物に過ぎず、機能は充分に発揮されません。
つまり、巡りという動きと、機能(役割)をセットで考えている点が東洋医学の特徴の一つと言えます。
巡りと機能はセットになっている。
この事は、漢方生活においても、所有する物に同じように当てはまります。私達の所有する物は何らかの機能(役割)を持つことは明らかです。物のもつ機能が、有効的に機能しているかどうかは、その物が置かれた状況によって異なりますが、物には機能(役割)が付属してきます。
次に、物が巡るとは一体どういう事でしょうか?
物を使用するとか飾るなど、その機能や役割を果たすように働きかける事だけではありません。もちろん、これらも物の巡りに含まれますが、これは狭い意味での物の巡りです。
漢方生活における物の巡りとは、物が置かれた状況や時間的経過に伴って、物の属するカテゴリが変化していく事を意味しています。
カテゴリが変わるとは、その物の必要性が変わったり、物を所有することで得られる心地良さが変わることです。必要性や心地良さが変わることで、物が持つ機能や果たす役割が変わることが、広い意味での物の巡りです。
これを図で表すとこの様になります。

図が示すように、必要性や心地良さについては、明確な線引きが出来るものではありません。。
多くの物が、その顔付きである4つのカテゴリのどこかには属していますが、いずれも固定的なものではなく、常に過渡的な状況下にあると考えます。
物の巡りを意識することで、所有する物との付き合い方を判断する視点を得る事になります。
物の巡りについてですが、良く巡る物もあれば、ほとんど巡らない物もあります。これらは相対的なものですから、優劣や善悪があるわけではありません。ただ、物には、その顔付きとなる4つのカテゴリを巡る性質がある事を確認するまでです。
まとめ
・物は、機能と巡りがセットになっている
・巡りには、狭い意味と広い意味の2つの巡りがある
・物は巡るので、所有する物のカテゴリ分けは過渡的で曖昧になりやすい

必要性や心地良さについては、明確な線引きが出来るものではないかもしれません。あるいは、個々人によって異なって良いものですから、無理やりに所有する物をカテゴリ分けする必要もありません。何となくフワっと物の持つ顔付きをとらえる視点として利用すれば良いですね。
所有する物の4つのカテゴリ分けに関する記事は>>>こちら
この様に、所有する物についてアバウトなとらえ方をするには理由があります。今回はその理由を考えながら物が持つ性質を漢方生活流に考えていきましょう。
漢方生活では、物は巡る性質を持つと考えます。これは、漢方生活の骨格をなす東洋医学の考えが元にあります。東洋医学では、体の中に取り込んだ物は、巡ることによってその機能を発揮する とされています。巡らなければタダの物に過ぎず、機能は充分に発揮されません。
つまり、巡りという動きと、機能(役割)をセットで考えている点が東洋医学の特徴の一つと言えます。
巡りと機能はセットになっている。
この事は、漢方生活においても、所有する物に同じように当てはまります。私達の所有する物は何らかの機能(役割)を持つことは明らかです。物のもつ機能が、有効的に機能しているかどうかは、その物が置かれた状況によって異なりますが、物には機能(役割)が付属してきます。
次に、物が巡るとは一体どういう事でしょうか?
物を使用するとか飾るなど、その機能や役割を果たすように働きかける事だけではありません。もちろん、これらも物の巡りに含まれますが、これは狭い意味での物の巡りです。
漢方生活における物の巡りとは、物が置かれた状況や時間的経過に伴って、物の属するカテゴリが変化していく事を意味しています。
カテゴリが変わるとは、その物の必要性が変わったり、物を所有することで得られる心地良さが変わることです。必要性や心地良さが変わることで、物が持つ機能や果たす役割が変わることが、広い意味での物の巡りです。
これを図で表すとこの様になります。

図が示すように、必要性や心地良さについては、明確な線引きが出来るものではありません。。
多くの物が、その顔付きである4つのカテゴリのどこかには属していますが、いずれも固定的なものではなく、常に過渡的な状況下にあると考えます。
物の巡りを意識することで、所有する物との付き合い方を判断する視点を得る事になります。
物の巡りについてですが、良く巡る物もあれば、ほとんど巡らない物もあります。これらは相対的なものですから、優劣や善悪があるわけではありません。ただ、物には、その顔付きとなる4つのカテゴリを巡る性質がある事を確認するまでです。
まとめ
・物は、機能と巡りがセットになっている
・巡りには、狭い意味と広い意味の2つの巡りがある
・物は巡るので、所有する物のカテゴリ分けは過渡的で曖昧になりやすい
タグ :物の巡り